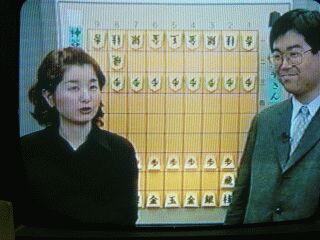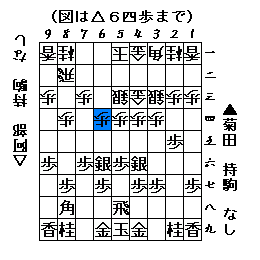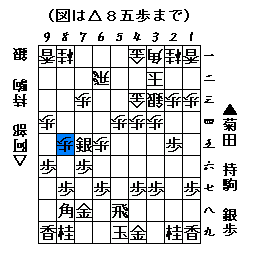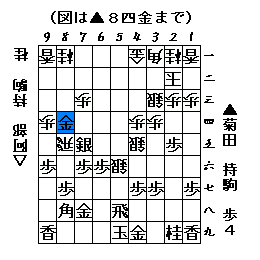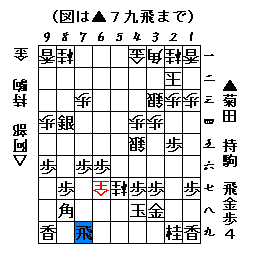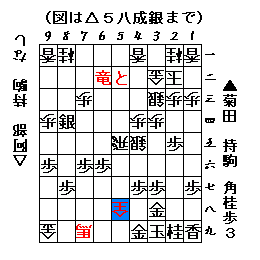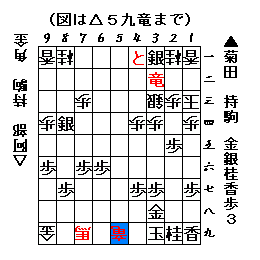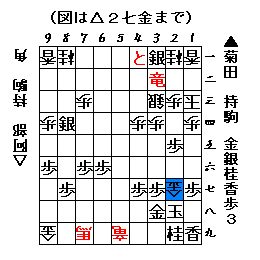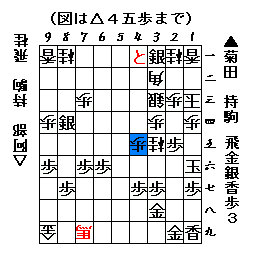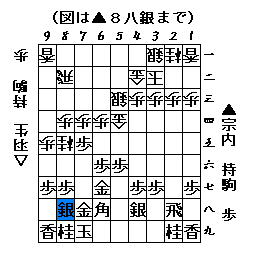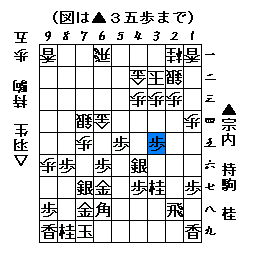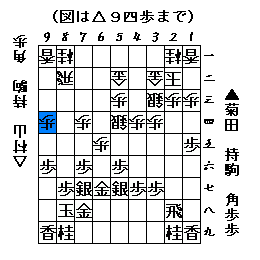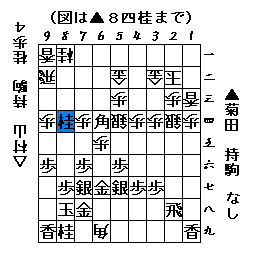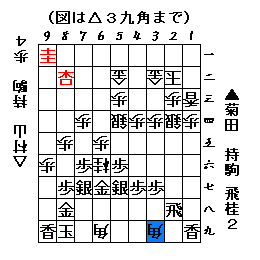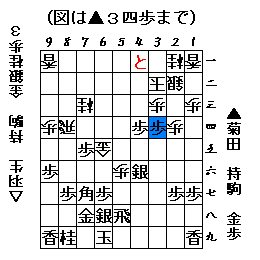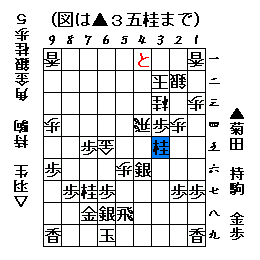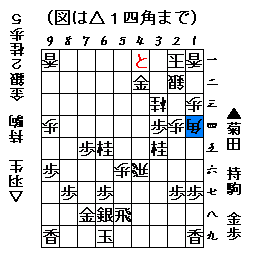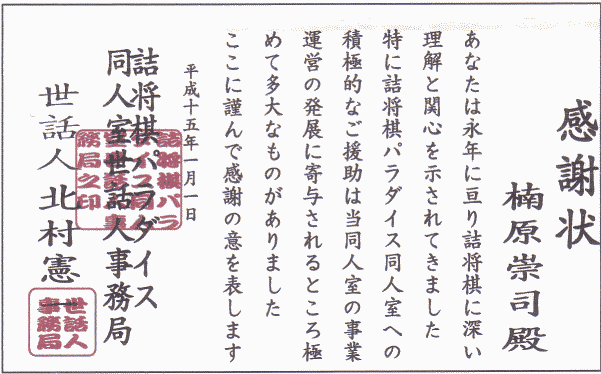『猫丸先輩の推測』(倉知淳、講談社)
2002年12月29日(日)
猫丸先輩みたいではないが、昨夜は帰省がてらに大学将棋部の先輩の家に逗留して、忘年会。
その折に、スカイパーフェクTVで放送されたお好み将棋対局(神谷七段との角落ち戦)のビデオを入手。(実は私は見れない)
そのもようをこっそりご紹介。(対局は勝ち)
↓聞き手・司会進行役は中倉宏美女流初段。
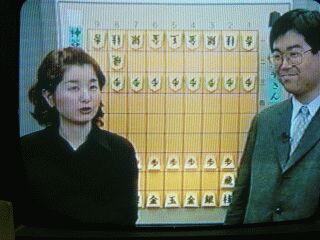
↓感想戦。解説は伊藤果七段。記録は大庭美樹女流一級。

1時間40分の長丁場なので、解説も困ったと思っていたけれど、詰将棋やなんやの話で案外つながっていたように思った。さすがプロだなあ、と、変なところで思ったけれども、いつもはどうやっているのだろうか?
『ミステリは万華鏡』(北村薫、集英社文庫)
2002年12月28日(土)
今日帰省するので、これが今年最後の更新。
将棋の棋譜ばかり載せていたので、とばしていた話題を記す。
Die Shwalbeが到来。世界大会の結果が載っている。
近代将棋が680円に値上げされた。
付録がついたが、これは羽生竜王の監修にしてはお粗末に過ぎる。値上げの理由は近将オープンなど、金がかかる企画を始めたからだろうが、将棋に関係のない文章を減らしてでも値段は据え置きにするべきだっただろう。せっかく、将棋世界がつまらなくなって、巻き返しの可能性が出てきたのだから。
その将棋世界は本日発売。
家を出るまでに届くかなあ?
『深夜特別放送 下』(ジョン・ダニング、ハヤカワ文庫)
2002年12月27日(金)
竜王戦第6局は羽生が勝って3勝3敗のタイとなった。決戦は年越しとなり、おおいに盛り上がっているようだ。
ということで、阿部先生にとっては残念であったが、七番戦いたいという当初の目標は達成された。
もっともこれは9戦目とも言えるけど。
さて、阿部六段(当時)VS菊田氏のアマプロ戦である。
木村九段が、解説で面白いことを書いている。
アマプロ戦はだいたい4、5段の新人棋士が相手になるが、8段以上のベテラン棋士も出てほしいという要望が多い。
筆者には話がきたことがないが、依頼されたら断るか、大金を要求しただろう。
とのことだった。
実に率直なコメントで、こういうことを屈託無く書ける木村先生は実に偉大だと思う。
新春お好み将棋対局 京都新聞夕刊平成5年1月13日〜22日掲載
先手:菊田裕司前アマ名人
後手:阿部 隆六段
(肩書きは当時)
▲7六歩 △8四歩 ▲6八銀 △3四歩 ▲7七銀 △6二銀
▲5六歩 △5四歩 ▲4八銀 △4二銀 ▲2六歩 △5二金右
▲2五歩 △3三銀 ▲5七銀 △4四歩 ▲4六銀 △4三金
▲5八飛 △5三銀 ▲9六歩 △3一角 ▲6六銀 △6四歩
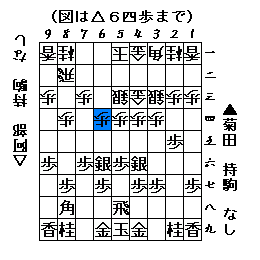
このころの菊田氏は、棋風を「オッサン将棋」と自称していた。その氏の採った作戦はカニカニ銀。
創始者の児玉七段を除けば、この戦法を大一番で採用できる人は、もしかしたら菊田氏だけかもしれない。
▲7五銀 △4二玉 ▲9七角 △3二玉 ▲5五歩 △6二飛
▲5四歩 △同 銀 ▲5五銀 △同 銀 ▲同 飛 △5四歩
▲5八飛 △6五歩 ▲7八金 △9四歩 ▲8八角 △8五歩
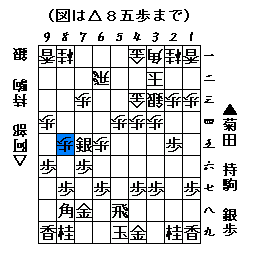
両者とも強気な性格で、感想戦で阿部プロが「これで作戦成功と思いました」に対して菊田氏「えっ」。
一見銀交換に終わっただけのように見えるが、そうでもないらしい。
▲7七桂 △2二玉 ▲8五桂 △8二飛 ▲6三銀 △6六歩
▲同 歩 △8五飛 ▲5四銀成 △同 金 ▲同 飛 △4五銀
▲5八飛 △5六銀打 ▲8四金
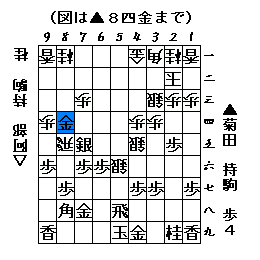
▲7七桂から▲8五桂と桂を跳ねる。狙いは歩得と、そして・・・
△8二飛から桂を取っている間に金を手に入れての▲8四金!
これまたアマチュアならではの手順と言えるのかも。
△同 飛 ▲同 銀 △5七桂
▲3八金 △6七金 ▲4八玉
△7八金 ▲同 飛 △6七銀成 ▲7九飛
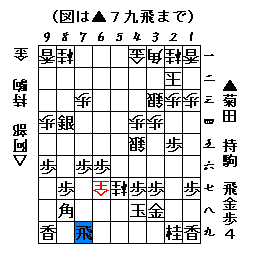
(全=成銀)
飛車を切った直後の△5七桂がおかしかったようだ。
ここは△5五桂が筋で、それなら切らすのは容易ではなかっただろう。
手順中▲4八玉は▲7九金で切れていた。
本譜でも▲7九飛で飛車を逃げつつ△4九金の一手詰を消して、後手の戦力は足りそうに無い。
△7八金 ▲8二飛 △4二角 ▲3九飛 △8八金
▲5三歩 △3二金 ▲6二飛成 △4九角 ▲5九金 △9九金
▲5二歩成 △9七角成 ▲5三と △4一香 ▲4九飛 △同桂成
▲同 金 △5五飛 ▲5二と △7九馬 ▲3九玉 △5八成銀
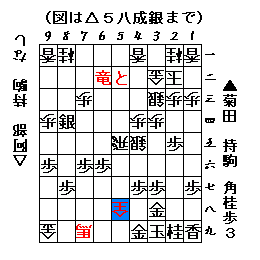
(全=成銀)
△7八金から角を取り返したものの、後手の戦力は分断され先手優勢は明らか。
しかし手順中▲4九飛が疑問手。▲5八歩くらいで切れていた。
▲同 金 △同飛成 ▲6五角 △5四銀 ▲4一と △1四歩
▲5四角 △同 龍 ▲3一銀 △1三玉 ▲3二龍 △5九龍
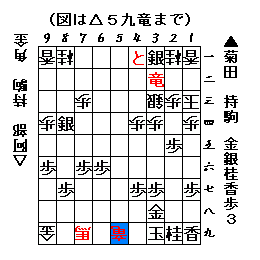
▲3二竜で受けなし。
終了かと思われたが、△5九竜が恐ろしい狙いを秘めた手。
▲2八玉 △2七金
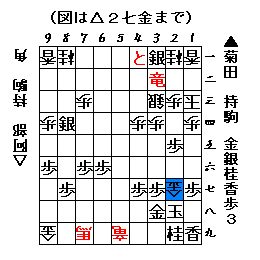
▲2八玉が大ポカ。▲4九金なら投了だっただろう。
△2七金が後手執念の一手。▲同金なら△4八竜以下詰む。
▲同 玉 △2九龍 ▲2八金打 △5四角
▲4五桂 △3五桂 ▲1六玉 △3二角 ▲2九金 △4五歩
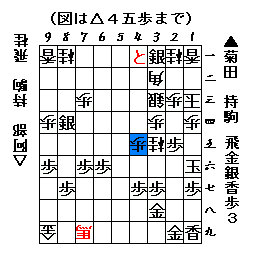
▲2七同玉に△2九竜が痛恨の一手。先に△5四角なら▲4五桂△3二角▲3三桂成に△6五角以下詰みがあった。
したがって、△5四角には▲3六歩△3二角▲2八金打が最善だが、秒読みでこんな切り替えができるとは思えない。
▲5三飛 △2四桂 ▲同 歩 △1五歩 ▲2六玉 △2四銀
▲3六玉 △4六飛 ▲同 歩 △同 馬 ▲2六玉 △3三桂
▲1六歩 △2五銀 ▲1五玉 △1四銀 ▲2六玉 △2五銀
▲1五玉 △2七桂成 ▲2二銀打
まで135手で先手の勝ち
手順中▲3六玉が詰めろで勝負あった。
最後は玉同士が向かい合っての千日手という面白い格好になった。
カニカニという奇異な序盤戦から終盤まで面白い応酬。
幻にしておくには勿体無いアマプロ平手戦だと思う。
こうして、菊田氏は京都新聞企画のアマプロ戦3連勝。「次はどうしましょう」と木村九段は内藤先生に相談したらしい。その返事が「後のことも考えて人選しなさい」だったそうで、ひとまずこのシリーズも終了とあいなった。
・・・こういうことを屈託無く書ける木村先生は実に偉大だと思う。
『ロシア幽霊軍艦事件』(島田荘司、原書房)
2002年12月26日(木)
竜王戦第6局は矢倉で駒がぶつかることなく1日目終了。
8五飛や藤井システムみたいな激しい展開の将棋が大流行なだけに、かえって珍しく感じる。
さて、宗内氏と羽生棋王(当時)は、羽生氏の八王子将棋センター時代からの因縁?の組み合わせだったそうだ。
宗内氏は矢倉で天才少年に挑む。
新春お好み将棋対局 京都新聞夕刊平成5年1月23日〜2月1日掲載
下手:宗内巌京都代表
上手:羽生善治棋王(角落)
△6二銀 ▲7六歩 △5四歩 ▲5六歩 △5三銀 ▲6八銀
△4二玉 ▲4八銀 △3二玉 ▲5八金右 △4二金 ▲2六歩
△7四歩 ▲6六歩 △6二金 ▲2五歩 △7三金 ▲6七金
△8四歩 ▲7七銀 △6四金 ▲7九角 △5五歩 ▲同 歩
△同 金 ▲5六歩 △5四金 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 角
△2三歩 ▲6八角 △6四歩 ▲7八金 △9四歩 ▲6九玉
△9五歩 ▲7九玉 △7三桂 ▲7五歩 △8五桂 ▲8八銀
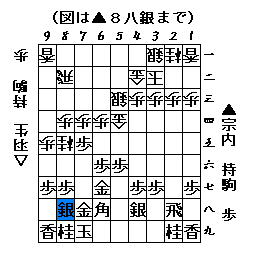
よくある矢倉の序盤戦だったが、△7三桂にスキがあった。すかさず桂を攻めるところは機敏。
△7五歩 ▲8六歩 △9七桂成 ▲同 銀 △2二銀 ▲8八銀
△6二飛 ▲5七銀 △9六歩 ▲9八歩 △6五歩 ▲7七銀
△6四銀 ▲6五歩 △同 銀 ▲6六歩 △7四銀 ▲4六銀
△6一飛 ▲3六歩 △8五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲8六歩
△7四銀 ▲3七桂 △1四歩 ▲5五歩 △6四金 ▲3五歩
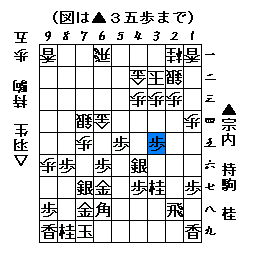
首尾よく桂得したが、その後下手は萎縮したような手が目立つ。
▲5五歩〜▲3五歩と位を取ったものの、決定打にはならない。▲4五銀とぶつけて決戦を挑みたかった。
△5一飛 ▲5八飛 △6三銀 ▲1六歩 △2四歩 ▲5九飛
△2三銀 ▲5六桂 △7四金 ▲4五銀 △8一飛 ▲5四銀
△5二銀 ▲4五銀 △8五歩 ▲同 歩 △同 金 ▲8七歩
△7六歩 ▲8八銀 △7五金 ▲4六角 △6五歩 ▲6九飛
△5八歩 ▲5四歩 △6六歩 ▲5七金 △6五金 ▲7三角成
△6一飛 ▲5八金 △5五歩 ▲6三歩 △同 飛 ▲同 馬
△同 銀 ▲6一飛 △5二金 ▲9一飛成 △5六歩 ▲3四歩
△同 歩 ▲1五歩 △6七桂 ▲6八玉 △7三角 ▲3三香
△同 桂 ▲1一龍 △5五香 ▲1四歩 △5七歩成 ▲同 金
△同香成 ▲同 玉 △4五桂 ▲同 桂 △5六歩
まで131手で上手の勝ち
後半は逆に一方的な展開となり、▲3三香△同桂が銀に当たるうえに、△5五香が詰めろとは。
序盤の桂損について、羽生棋王は「▲9八歩と打たせて少し得と思いましたが、やはり桂得のほうが大きいですね」とコメント。
なぜか中盤の解説で、私の指摘が引き合いに出されている。「▲9八歩は▲8七銀では」感想戦で口出ししたらしい。
「この2人は攻め七分なので屈服が嫌い」などと、木村九段にひとくくりにされているのが、ちょっと嬉しい。
さて、明日はいよいよ、阿部六段(当時)VS菊田さんのアマプロ平手戦をアップしようと思う。
『絶対泣かない』(山本文緒、角川文庫)
2002年12月25日(水)
村山聖六段(当時)と菊田アマ名人の平手戦は、この年の棋王戦の前座対局として、平成四年二月十四日に行われた。
京都新聞の記事によると、木村九段からこの企画を依頼された村山六段は、「羽生さんが角落ちでボクが平手ですか。ムニャムニャ」と言ったそうである。『聖の青春』でも見られる羽生への対抗意識からは、当然かもしれないが。
解説の木村九段は、菊田氏の対プロ戦績も素直には評価しない。「並みのプロには勝っているが有望プロには負けているようす。」と書いているが、これは如何なる含みを持っているのだろうか?
第18期棋王戦前座対局(平手) 京都新聞夕刊平成4年2月27日〜3月6日掲載
先手:菊田裕司アマ名人
後手:村山聖六段
(肩書きは当時)
▲7六歩 △3四歩 ▲4八銀 △8四歩 ▲5六歩 △8五歩
▲5七銀 △6二銀 ▲7八金 △3二金 ▲6九玉 △4一玉
▲5八金 △6四歩 ▲2六歩 △6三銀 ▲2五歩 △8六歩
▲同 歩 △同 飛 ▲8七歩 △8二飛 ▲2四歩 △同 歩
▲同 飛 △5二金 ▲1六歩 △5四銀 ▲2六飛 △2三歩
▲1五歩 △4二銀 ▲2二角成 △同 金 ▲8八銀 △7四歩
▲2八飛 △3一玉 ▲6六歩 △3二金 ▲6七金右 △4四歩
▲7七銀 △6五歩 ▲7九玉 △6六歩 ▲同銀右 △6五歩
▲5七銀 △2二玉 ▲8八玉 △3三銀 ▲9六歩 △9四歩
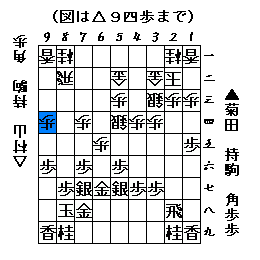
互いに飛先の歩を交換するという珍しい矢倉。
手を出すところがないようだが、菊田氏の見せた手順は、いい意味で「いかにもアマ」といった構想だった。
▲1七桂 △2四銀 ▲2五桂 △6九角 ▲1四歩 △同 歩
▲1二歩 △同 香 ▲1三歩 △同 桂 ▲6四角 △9二飛
▲1三桂成 △同 香 ▲8四桂
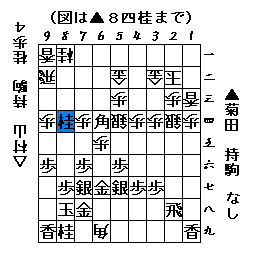
端で桂を手に入れて▲8四桂。敵陣を耕し、入玉を狙う。これに泣かされたアマチュアは数知れず。
結果として、△1三同桂が▲6四角〜▲8四桂を見落とした疑問手だった。もっとも、△1三同香なら香を手に入れて▲8四香とするのだろうが。
△9三飛 ▲7二桂成 △9五歩
▲8一成桂 △9六歩 ▲9一成桂 △9七桂 ▲8二角成 △9四飛
▲8六銀 △8九桂成 ▲同 玉 △6六桂 ▲8八金 △8四飛
▲8五香 △8二飛 ▲同香成 △8五歩 ▲7七銀 △3九角
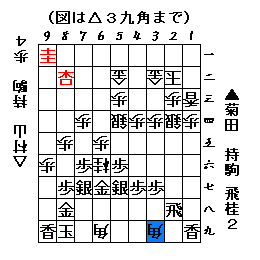
(圭=成桂、杏=成香)
▲8四桂から根こそぎ攻め駒をそぎ取る。
こういう最初から寝技を狙うような手順は、あまりプロでは見られないのだろうか?ここから後手の手が乱れる。
△8五歩は▲7七銀と引かせて損だった。
△3九角が敗着。△5八桂成としてチマチマ攻めるのだった。
飛角が渡ると飛車打ちに対して、後手玉は適当な受けがない形なのだ。
▲3八飛 △5八角成 ▲6八銀右 △6七馬 ▲同 銀 △5七角成
▲6八銀 △4七馬 ▲1八飛 △6九馬 ▲8一飛 △3三玉
▲3六桂 △3五銀 ▲2五桂 △4三玉 ▲2一角 △4二金右
▲1三桂成 △8六歩 ▲7八香 △3六銀 ▲同 歩 △9七桂
▲9八玉 △7八桂成 ▲同 銀
まで117手で先手の勝ち
▲3八飛以下は完封勝利。
手順中、▲1三桂成が確実な寄せであり、▲7八香の受けを用意した、「おいしい一手」である。
さて、こんなふうに刈り出したご自慢のプロをあっさり撃破されては、京都新聞社は引っ込みがつかない。
ということで、ふたたび翌年の新春お好み対局で、菊田さんに若手プロをぶっつけた。
それが、今をときめく阿部隆六段(当時)。
新進気鋭のプロに、菊田さんがどう挑むのか?乞うご期待!
と、その前に、振り返ってみると平成五年のお好み対局にはもう一局、羽生善治棋王(角落ち)VS宗内巌京都代表 という取り組みがあった。(もう一戦は、内藤九段VS河原林アマ代表の角落ち戦だった。)
宗内氏は京大4年生(当時)で、90年の学生名人。これまた対プロ平手戦2勝1敗という戦績を誇る将棋部のエースだった。
だから、今思えば、この年のお好み対局は、現在、竜王戦で死闘を繰り広げているこの二人と、京大将棋部のプロキラーの対決という構図だったのだ。
ということで、竜王戦第6局記念として、明日は羽生VS宗内戦、あさってに阿部VS菊田戦をアップしようと思う。
『聖夜に死を』(西村京太郎、徳間文庫)
2002年12月24日(火)
覚えておられる方もいるかもしれないが、菊田アマ名人はNHKのアマ名人記念対局で、羽生名人と角落ちで戦い、負けている。おまけに飛落ちも拾い勝ちだった。しかし、この二人はこれとは別のところで、相見えていたのである。
京都新聞新春お好み対局(京都新聞平成4年1月4日〜13日掲載)
下手:菊田裕司アマ名人
上手:羽生善治棋王(角落)
△6二銀 ▲7六歩 △5四歩 ▲6八銀 △5三銀 ▲5六歩
△4二玉 ▲4八銀 △3二玉 ▲7八金 △8四歩 ▲6九玉
△8五歩 ▲4六歩 △7四歩 ▲5七銀右 △7二金 ▲4五歩
△7三金 ▲3六歩 △6四歩 ▲3五歩 △2二銀 ▲4六銀
△6五歩 ▲5八飛 △6四金 ▲4八金 △5二金 ▲9六歩
△2四歩 ▲4七金 △8六歩 ▲同 歩 △同 飛 ▲8七歩
△8四飛 ▲5五歩 △7五歩 ▲同 歩 △7三桂 ▲3七桂
△6六歩 ▲同 角 △6五金 ▲7七角 △9四歩 ▲4四歩
△5五歩 ▲4三歩成 △同 金 ▲4五桂 △4四銀 ▲5三歩
△5四金 ▲5二歩成 △4五銀 ▲4三歩 △4一歩 ▲同 と
△4三玉 ▲4五銀 △同 金 ▲4六銀 △5六金左 ▲同 金
△同 歩 ▲4四歩 △3二玉 ▲3四歩
菊田「最初から普通の将棋(矢倉)にする気はなかった」
とのことで、二枚落ちの2歩突っきり風の戦型となった。
ごちゃごちゃとした押し合いへし合いの末、この局面になった。もちろん、すでに角落ちとしては紛れた格好だ。
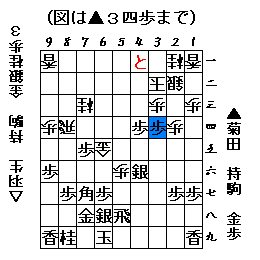
△8五桂 ▲3三歩成
△同 桂 ▲3四歩 △7七桂不成▲同 桂 △4四飛 ▲3五桂
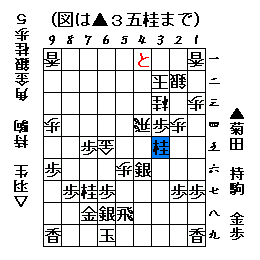
△8五桂?が疑問手。角を取っても桂を渡したうえに、金当たりになってしまう。
その桂を3五に据えて勝負あったか?
△4六飛 ▲4二金 △2一玉 ▲6五桂 △1四角
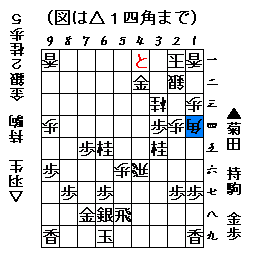
▲6五桂は手拍子。▲3三歩成△同銀▲2三桂成で決まっていた。
△1四角は詰めろ逃れの詰めろ。いわゆる「羽生マジック」か。
秒読みでこんな事態になったら、普通はガタガタになるものだが。
▲3二金打 △1二玉 ▲2二金 △同 玉 ▲2三銀 △同 角 ▲同桂成
△同 玉 ▲3三歩成 △1四玉 ▲3四角 △4七銀 ▲2六桂
△同 飛 ▲同 歩 △5八銀成 ▲同 玉
まで100手で下手の勝ち
冷静に角を外して、▲3三歩成とすると、王手飛車があるため取ることができない。
玉を端に追いやって▲3四角が決め手。菊田氏が勝利したが、この後に行われたテレビ対局では、羽生名人が(本気を出して?)雪辱を果たした。
さて、この年の富士通杯では菊田裕司アマ名人のプロ撫で斬り事件が起こっている。
今ではアマがプロに勝つなんて珍しくもないが、当時はそういう棋戦が多くはなかったからか、かなりの椿事だった。
このため、京都新聞社としては、今回の手合いには悩んだらしい。羽生名人が相手なら当然角落ちになるだろうが、将棋ファンは菊田氏のプロキラーの腕前を見たいと思っているだろう。
そんなわけで、京都新聞社は、京都で行われた棋王戦の対局の前座対局として、菊田さんに村山聖六段(当時)をぶつけるという企画を催した。手合いは平手。
村山聖VS菊田裕司・・・
今考えてみれば、相当無茶な企画で、よく村山プロが受けたものだと思うが、そのころの菊田氏の活躍はそういった常識を覆すだけの勢いがあった。
その結果は・・・明日のお楽しみ。
『イブの憂鬱』(唯川恵、集英社文庫)
2002年12月23日(月)
イブの憂鬱ならぬイブイブの憂鬱。てゆうか、早い話が二日酔いで頭が痛い。
* * *
プロブレム・パラダイス第23号が到来。ポルトロス大会と世界創作チャンピオン戦の結果が掲載されている。
上田吉一さんのフェアリー作品集『極光II』の予告記事が載っている。と、同時に、私の5手詰作品集の予告も。
これを勝手に補完しておくと、作品集の題は、『五・手・詰』(うる・てぃ・めいと)とする予定。題に沿った内容にするべく、年末年始をかけて執筆するつもりだ。
* * *
さて、私が大学にいたころの京都新聞主催の新春アマプロ戦は、マニア垂涎の対決が演じられた「知られざるアマプロ戦」であった。その面白いいきさつをここでこっそり公開しようと思う。もちろん、内容は当時の京都新聞に掲載されている記事をもとにしており、創作や脚色はない。
まずこのアマプロ戦の仕組みを説明しておこう。京都新聞の夕刊には地元の大会などのアマチュアの棋譜が載る。このコーナーに1月から載せる将棋を、その前年の暮れくらいに行う。アマ側は京都・滋賀の県代表2人と高校代表1人が選抜される。プロ側はだいたい関西在住プロだが、京都新聞社が棋王戦のスポンサーをしている関係で、当時の棋王も呼んでくるのだからたいしたものだ。ちなみに当時の解説は木村義徳九段である。
平成四年(対局は平成三年)の取り組みは以下のとおりだった。(肩書きは、当時)
羽生善治棋王(角落) VS 菊田裕司アマ名人
村山 聖六段(飛落) VS 樋口純平高校代表
桐山清澄九段(角落) VS 山田康平京都王将
羽生VS菊田戦の棋譜は明日以降に。
なお、私が「京都王将」という肩書きで出ているが、これは京都新聞社主催のローカル大会。全国に繋がるものではない。ついでに結果を言うと、途中まではまともに指したものの、寄せの入り口で誤り、負けている。
『ホロウ・ボディ』(米田淳一、ハヤカワ文庫)
2002年12月22日(日)
相当にベタな設定のSF活劇で、ゲーム『ゼノサーガ』にたいへん似ている感じ。ただ、どちらがどちらをパクったのかは知らないが。
まあ、そういうマニアックな分析はともかく、
「あなたたちの手筋に、正しい手は一つもない」
「彼らは『詰めろ』で来ている」
「お互い、手筋のヨミ合いを競ってここまで来た」
なんてソレっぽい表現がそこかしこに見られる。この作者はいったい何者なのだろう?
もちろん「オマエモナー」なんて台詞を平気で使っているのも、妙なのだが。
* * *
将棋仲間と研究会&忘年会&菊田裕司氏東京チャンピオン戦優勝祝賀(たかり)会。
東京チャンピオン戦については、http://homepage2.nifty.com/toushouren/chanpion12.htm
をご覧ください。
『深夜特別放送 上』(ジョン・ダニング、ハヤカワ文庫)
2002年12月21日(土)
神崎健二七段のホームページの日記で、京都新聞の新春将棋対局の話題が載っている。このころ高校選手権の代表になったこと関係で、この企画に出場し、たしかに角落ちで教えていただいたのだけれど、正直言って、将棋の内容はきれいさっぱり忘れてしまっていた。
・・・ていうか、神崎先生にはもともと何度も教えていただいてたからなぁ。角落ちではほとんど勝てなかったけど。
さすがに忘れてしまったままでいるというのはあまりにも失礼なので、国会図書館まで行って京都新聞のマイクロフィルムを閲覧してきた。それで掘り出したのがこの棋譜。
平成元年新春お好み将棋対局角落ち戦
上手 神崎健二四段 (当時)
下手 山田康平京都代表(高校2年生)
△6二銀 ▲7六歩 △5四歩 ▲5六歩 △5三銀 ▲5八金右
△6四歩 ▲6六歩 △4四歩 ▲4八銀 △5二金右 ▲6七金
△4二玉 ▲4六歩 △3二玉 ▲7八銀 △3四歩 ▲3六歩
△4三金 ▲4七銀 △6二飛 ▲7七銀 △6五歩 ▲同 歩
△同 飛 ▲6六歩 △6一飛 ▲7八金 △7四歩 ▲6九玉
△4二金直 ▲2六歩 △2二銀 ▲2五歩 △3三銀 ▲7九角
△1四歩 ▲1六歩 △6四銀 ▲6八角 △7五歩 ▲同 歩
△同 銀 ▲7六歩 △6四銀 ▲7九玉 △7三桂 ▲8八玉
△8四歩 ▲3七桂 △8五桂 ▲8六銀 △6五歩 ▲5七角
△5五歩 ▲6五歩 △同 銀 ▲6二歩 △7一飛 ▲8四角
△6六歩 ▲同 金 △8一飛 ▲8五銀 △8四飛 ▲同 銀
△6六銀 ▲8一飛 △3九角 ▲2七飛 △5七角成 ▲2四歩
△同 歩 ▲2五歩 △6七歩 ▲2四歩 △2二歩 ▲2八飛
△4七馬 ▲2五桂 △2四銀 ▲3三桂打 △同 桂 ▲同桂成
△同金寄 ▲5四桂 △5二金 ▲1一飛成 △2一金 ▲1四龍
△2三銀 ▲2五歩 △1四銀 ▲2四歩 △4六馬 ▲4八飛
△5七馬 ▲2八飛 △7七歩 ▲同 桂 △6九飛 ▲5八銀
△7七銀成 ▲同 玉 △6五桂 ▲8八玉 △6六馬
まで107手で上手の勝ち
うーむ。圧敗。たしかにこの内容では、忘れたくもなるのも無理はない。
さて、この年ふたたび高校代表に(しかも、高校名人にも)なったため、翌年の新春対局にも出て、そのときは浦野真彦六段(当時)との角落ちで教えていただき、雪辱しているが、実はそれも拾い勝ちに過ぎない。
振り返ってみると、昔の将棋は荒っぽいなあ。(今もたいして変わらんか)
さて、さらにその先、大学に入ってからの京都新聞の新春企画も検索してみると・・・この頃の面白い棋譜を再入手できた。今後ここでこっそりアップしようと思う。
『仙山線殺人事件』(津村秀介、青樹社文庫)
2002年12月20日(金)
仙台と天童で真剣師の将棋大会が行われ、それに参加した2人の真剣師が仙台と山形のホテルで相次いで殺される、というミステリー。容疑者も真剣師で、探偵は将棋三段の新聞記者。真剣が絡んでいるためか、日本将棋連盟は影すら見せず、プロ棋士のひとりも出てこないというのは、将棋に関連した小説としては珍しいのではないだろうか。
なお、推理小説としては、単なるアリバイ崩しで、すぐに真相が分かってしまうため、あまり推理を楽しめない作品だった。
『五月はピンクと水色の恋のアリバイ崩し』(霧舎巧、講談社)
2002年12月19日(木)
「柿木将棋VII」を入手。
私のパソコンは現在スタンダードなものよりちょっと落ちる(WindowsもMe)けれど、それでもパラの裸玉を7分で解くというスグレモノである。もっとも使うのは人間だから、使いどころが肝心なわけだが。
非限定を検出してくれるのはたいへん便利。「連続検討機能」も役に立ちそうだ。思うに、これからの詰将棋作家にとって、コンピュータチェックは必須となるのではないか。もっともそれは、チェスプロブレムでは、大部分すでにそうなっているのだけれど。
『定跡外伝』(毎日コミュニケーションズ編、MYCOM将棋文庫)
2002年12月18日(水)
こんなことを書くと高橋和女流のファンは、おそらく激怒すると思うが、書く。
今回の御婚約は、たいへんおめでたいことだ。
しかし、棋士を続けるというのは、みな喜ばしいといっているが、正直言って疑問だと思う。
所詮、大部分の将棋ファンや関係者は、彼女をアイドル視したり人寄せパンダとして扱ったりしているのだし、そのせいでテレビで言っていたように、自律神経失調症にまでなったというのなら、いっそのこと、これを好機として指将棋には見切りをつけるという手もあるのではないか?
私は、指すほうは引退して、海外への将棋普及活動と、詰将棋の創作を続けるというのも立派なことだと思う。
普及活動を進んでできるヒトというのは、ただ棋力や技術が高い以上に貴重な存在なのだ。
また、女性が詰将棋をどこまで極められるのか、未知の可能性を彼女は見せてくれるかもしれない。
ただし。。。
こんなことを書くと詰キストはおそらく激怒すると思うが、書く。
残念なことに、詰将棋界の連中も、アイドル視や人寄せパンダという面では同類である。
いや同類どころか、歴史的に考察すると、それ以上にひどいかもしれない。
そこで、チェス・プロブレムはどうだろうか?
流石の彼女でも、人寄せ効果がない、ディープでマニアックな世界だから、かえって気軽だと思うが。
ちなみに、チェス・プロブレムの世界大会には、女性もかなり参加している。
大部分は同伴者としてだけれど、解答選手権に出ている方もいるし、創作の方面でも、今年のJapanese Sake Tourney に作品を寄せられたり。それを紹介しよう。
Anna O'Donovan (Great Britain)
Japanese Sake Tourney
a) Shortest proof game in 7.5 Haunted Chess
b)  g8->f5 Shortest proof game in 8 Orthodox Chess
g8->f5 Shortest proof game in 8 Orthodox Chess
(Solution)
a)1.h4 a5 2.h5 a4 3.h6 a3 4.hxg7 axb2 5.Rxh7 Rxh7 6.a4 Rh8(+wRh7) 7.gxh8=R(+wPg7) bxa1=R 8.Rxg7.
b)1.a4 Sh6 2.Ra3 Sf5 3.Rh3 h6 4.Rxh6 a6 5.Rxa6 Rxh2 6.Rg6 Rh3 7.Rxg7 Ra3 8.Rh8 Ra1.
a)ではwRh8,bRa1は成駒なのだが、b)では生駒というのがテーマ。変える要素がちょっと多目だが、言いたいことはよくわかる。
『運と気まぐれに支配される人たち』(ラ・ロシュフコー、角川文庫)
2002年12月17日(火)
「女性に入れ込み、その度に銃弾にまみれるという生き様は、まさにフランスの「ドン・キホーテ」」による箴言集。
こうした先達の貴重な経験が我々の明日を照らす道標になるのである。。。
人は、せっせと善行を積む。あとで悪事を働いても大目に見てもらえるように。
この道一筋といっても、べつに非難するにも、賞賛するにも当たらない。というのは、趣味や感覚が、いっこうに変わりも殖えもせず、持続しているにすぎないのだ。
弱い人は、誠実ではあり得ない。
若くても、美しくなかったら、なんにもならぬ。
美しくても、若くなかったら、なんにもならぬ。
これはちょっとひどい出来のものを抽出したので、ホントはもっといいのがあるのだけれど。
『低音火傷 3』(狗飼恭子、幻冬社文庫)
2002年12月16日(月)
最後に近づくにつれ、息詰まる展開。これこそまさしく狗飼節。
おそらく、つまらないという人もいるだろうし、批判もあるかもしれないし、素直に感動できない事情の方もいるだろうが、私は間違いなく、本作は作者の代表作になると言い切れる。どうしてこの作者はこれほどまで登場人物に思いを重ねさせることができるのだろうか?
* * *
高橋二段が婚約とのこと。相手は大崎善生氏。おめでたいことであるが、びっくりした。
何がびっくりしたかというと、あの大崎氏が独身だったということ。
氏の著作からみるに、あと年代的に、独身だというのは意外だった。
まあ、ともあれ、おめでとうございます。
ということで、結婚祝賀詰「ヨシオ」でも作ろうかと思ったが、どうもこの名前は1つの盤に収まりそうにない。
男性より女性の名前のほうが詰将棋を作りやすいように思える。
おそらく、詰将棋の神様は男性なのだろうな。
* * *
『CHESS通信』が来る。スロベニアで行われたチェスオリンピアードの記事が載っている。それによると試合開始前にドーピングテストをやるらしい。「ポケットコンピュータを持っているかどうかコンピュータ・ドーピングのテストの方が必要だ」という一選手のコメント。ケイタイや小型PCの所持検査はしていないのに、薬物検査はやるのか。あいかわらず『CHESS通信』は面白い。
『カンキの双玉詰将棋傑作選 上巻』(神吉宏充、毎日コミュニケーションズ)
2002年12月14日(土)
上巻108作を見た限りでは、同じような作品ばかりのように思えた。
たとえば、第15問、第39問、第53問、第76問、は同じネタである。
第19問、第48問、第49問、第79問、もよく似た一群だ。
第3問に至っては、第83問の収束5手を抜き出したもの。
『傑作選』とまで銘打っているのだから、もうちょっと「選」んだほうがよかったのではないかと思う。
『トム・ゴードンに恋した少女』(スティーヴン・キング、新潮社)
2002年12月13日(金)
私のようなお気楽さんでも、たまには悩みや苦しみや、辛さや惧れに襲われて、打ちのめされるときがある。
でもこの本を読んでみたら、なんだ、そんなのたいしたこっちゃねえ、と生き返る。
そういう単純な俺は、やっぱり、もとより悩みや苦しみや、辛さや惧れに無縁なお気楽さんなんだろうなぁ。
今日はオチ無しね。
『魔神の遊戯』(島田荘司、文藝春秋)
2002年12月12日(木)
詰将棋グラフィック・アートに『喪中詰』をアップしていたら、どうにもおかしい。盤面の画像ファイルは半分ゆがんでしまうし、「動く将棋盤」は白紙になってしまう。
調べてみたらどうやらサイトの所定の容量をオーバーしてしまう瀬戸際らしい。
さっそく拡張を申し込むが、2年目で10メガバイト超えてしまうとは。結構無駄な使い方をしているのだろうか?
* * *
竜王戦サイトの詰将棋のコーナー。
高橋女流の作品には誰かが余詰指摘をしたらしく、お詫びのメッセージが出ている。
しかし、「無理にお願いした高橋二段にもお詫び」というのもよくわからない。
「無理に」なんてつけるのは、失礼だと思う。あの作品は出来は良くないが、新味あるものを求めようとする意志は伝わってくる。無理にというなら、あそこに並んでいる大部分の棋士の方々にお詫びしなければならないだろう。詰将棋は余詰がなければいいってものでもないのだ。
ところで色紙の画像の上の作者名が、普通は「田中寅彦九段作」とか「丸田祐三九段作」なのに、森内先生だけ「森内名人作」となっているのはなぜだろう。
『ヤーンの時の時』(栗本薫、ハヤカワ文庫)
2002年12月11日(水)
楠原崇司による後編がアップされた。鯨統一郎の『邪馬台国はどこですか』を意識したけれど、どんなもんだろうか。
↓「将棋の起原−On the Origin of Shogi−解決編」(リレーエッセーその58)
http://www.af.wakwak.com/~mtmt/shogi/essay/essay058.htm
林真須美被告への判決が出たけれど、直接の動機は判明せず、証拠もどちらかというと間接的なものだったらしい。
現代の事件においても、時間をかけて審理してこんなものなのだから、歴史の謎を遡るというのは、相当難しいと思う。
断片的な事実を積み重ね、あとは想像力にたよるしかない。しかし、そういった産業や技術といった生活に密接なものならば断片的な事実が有効であるが、ゲームのような、特段必要性の乏しい分野においては、むしろ事実に頼るより想像力が重要となると思われる。なぜなら、生存に直接関係のない文化は、伝播の必要性がそもそも乏しいことから、距離とともにその影響は廃れてしまうからだ。日本の将棋に、チェスのキャスリングや中国将棋の不対面ルールがないのは、それが吟味の結果採用を見送られたのではなく、そもそも彼らがそれを知らなかったからなのだろう。
『マネー、マネー、マネー』(エド・マクベイン、ハヤカワ・ポケット・ミステリ)
2002年12月10日(火)
帰ったら若島先生から封筒が届いた。なかに書籍がはいっているらしい。
これはいよいよ、『極光2』が出来たのか!と思って着替えるまもなく開封すると、出てきたのは『羽生の奥義12』。
チェス将棋交流協会からの報告だった。がっくり。
* * *
竜王戦第4局は、羽生がまさかの逆転負け。投了図は大部分の駒が持駒にあって、まるでチェスの終盤みたいだった。
これで将棋世界の予想クイズははずれ。がっくり。
* * *
将棋パイナップルのサイトのリレーエッセイの順番が廻ってきたので、こないだ思いついたネタで楠原崇司へのつなぎの駄文がアップされた。それにしてもこのネタは興味のあるかたが多いようだ。座布団投げつけられるのが怖い。。。
↓「将棋の起原−On the Origin of Shogi−問題編」(リレーエッセーその57)
http://www.af.wakwak.com/~mtmt/shogi/essay/essay057.htm
『名探偵Z』(芦辺拓、ハルキ・ノベルス)
2002年12月09日(月)
なんか寒いと思ったら大雪。
* * *
同人室事務局の北村憲一さんから手紙。開けてみたら、楠原崇司への感謝状だった。
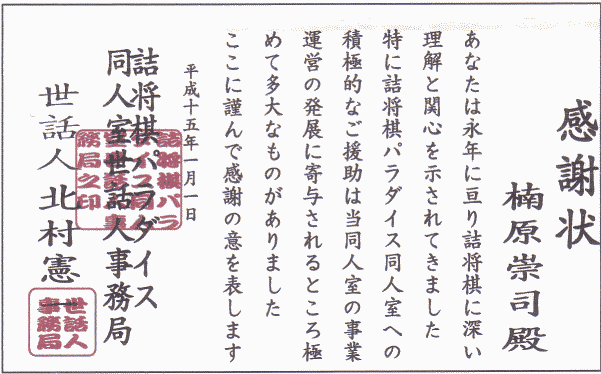
どうやら、『BlueFile』や『看寿殺人事件』を賞品用に提供したことが評価されたらしい。
冗談にしても光栄である。
『島ノート』(島朗、講談社)
2002年12月07日(土)
おんなじような図面がひたすら続く退屈な定跡書とは異なり、エキサイティングでかつ最新の戦法が幅広く解説された良書。
ただ、形勢判断は棋風で判断の別れるところもあるように思う。
* * *
A級順位戦は1敗の谷川・羽生がともに敗れて大混戦になっている。落ちるほうも1勝がいないから、ますます激戦である。
今年の女流名人戦で最終局がインターネット中継されたから、当然A級も全局中継となるのだろうか。
『侵入者』(小林信彦、メタローグ)
2002年12月05日(木)
詰パラがまだこない。都内でまだ来ていないというヒトが多いので、これはおそらく郵便事故だろう。明日本屋で立ち読みしようと思う。
京都民報の原稿依頼。明日締め切りということであわてて創る。しかし、新年の出題は例年のごとく趣向問題にしてほしいとのこと。ちょっと考えてみるか。
『虹の天象儀』(瀬名秀明、祥伝社文庫)
2002年12月04日(水)
今日チャットで教えてもらったが、ノーシンのコマーシャルで詰将棋がテストに出題されるというのを今やっている。詰将棋もここまでメジャーになったのか、とびっくり。
URLは、 http://www.arax.co.jp/tvcm/ で、「イタがらナイスデー日記 テスト編」というやつ。図面が小さくて、作品の内容まではよくわからないけれど。
『低温火傷 2』(狗飼恭子、幻冬社文庫)
2002年12月03日(火)
ハリーポッターの映画を観た。今回はチェスのシーンがなくて残念。(てゆーか、前作も原作は読んだものの、シーンは電器屋のプロモーションで目にしただけだけれど)
* * *
それにしても詰パラがこない。なぜだろう。
『なんでも屋大蔵でございます』(岡嶋二人、講談社)
2002年12月02日(月)
将棋世界1月号が到来。
相手の玉に詰みがある状態で投了したという話が出ている。
アマチュアだと投げっぷりが悪いから、却って起こりそうにないポカだと思う。
田辺氏の「ずばり提言」という記事がいきなり載っている。氏にとっては「王様」という呼び方が「いまわしい」らしく、『王様」と呼ぶのなら「お龍さん、金さん、銀さん、お桂ちゃん、お香も使ったらどうか。玉将は最近はやりの「たまちゃん」でよろしい」これは微妙だ。』などとけったいなことを書いている。こんなのは冗談としか思えないが、最後に『願わくば二上達也会長より、「公の場における王様の連呼は禁止する」との通告を会長名で出してもらえないだろうか』などと訴えているあたり、真面目なつもりらしい。
しかし、「玉」を「オオサマ」という呼び方はそれほど気にならない。「香」を「ヤリ」と呼んだり、「歩」を「ヒョコ」と読んだりするよりは、自然な気がする。将棋のロイヤル駒がもともとは「王」はなくて「玉」だけだったという説があるが、もしそれが本当だとすると、「王手」という言葉はあるのに、なぜ「玉手」という言葉がないのか私にとって不思議でならない。
私はむしろ、良くないのは紛らわしい呼び方である。「桂馬」を「馬」と呼ぶのは禁止したいと思う。また、「玉」を「キング」、「飛車」を「ルーク」というように、翻訳の際にチェスの似た駒にこじつけるのも、それらの性能が異なることから好ましくない。ただそれは、「玉が正しくて王が間違いだから、キングと呼ぶな」という主張とは論旨がことなるけれども。
『我が屍を乗り越えよ』(レックス・スタウト、ハヤカワポケットミステリ)
2002年12月01日(日)
三浦三崎マグロ大会に出場するが、勝ちたくないような手を連発し、結局参加賞のワカメを獲得するのみ。どうも、弱すぎる。
ホームへもどる