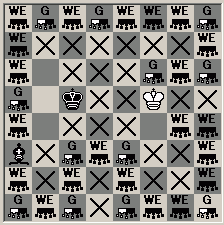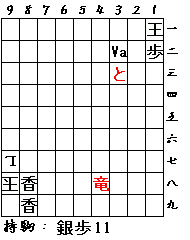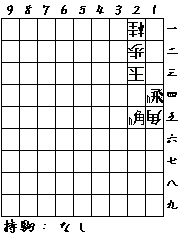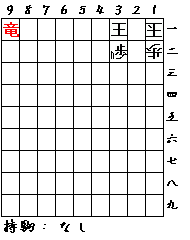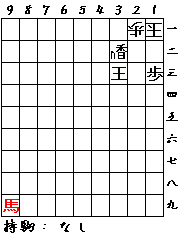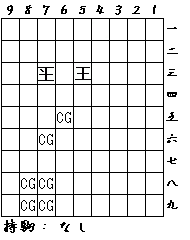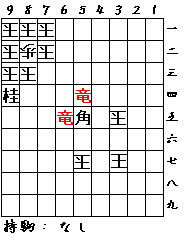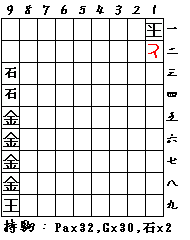�w�R�H�Q�x�iB.A.�j�`�P�`�C�I�N�AUral Problemist�j
2003�N08��31���i���j
�G���h�Q�[���̃A���\���W�[�ŁA�Q�W�O��قǎ��^����Ă���B
���X�N���̑��ŁA��t�̂Ƃ��ɂ����������t�H���_�[�ɓ����Ă����{�̂ЂƂB
���{�̋l�����S�����̎�t�̂Ƃ��ɁA�S���Ɂw�������i�W�E���S��x��z��悤�Ȃ��̂��B
�����A���̓G���h�Q�[���͂悭�킩��Ȃ��B
�����悤�ȍ�i����Ɍ����āA�ǂ��ɍH�v���������炢���̂��킩��Ȃ��̂��B
�����A�Ō�̕��ɍڂ��Ă����ȑf�`�̍�i�́A���������������B
����͍ŏ��̂ق������ǁAQ�����������̂ŁA���Љ�B
CA.Ce�|�y�ra�~o�r���}
MK�H.�A�y���~o�ra ,1987
Win
1.Sg5 c3 2.h7 c2 3.h8=Q+ Kb1 4.Qh7 Kb2 5.Qg7+ Kb1 6.Qg6 Kb2 7.Qf6+ Kb1 8. Qf5 Kb2 9. Qe5+ Kb1 10.Qe4 Kb2 11.Qxb4+! Ka1 12.Qd2! Kb1 13.Se4! c1=Q 14.Sc3+
�Ɍ��h�h�̑�W�V�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�A�W��A�p�I�A�����p�I�A������g�p�A�c�C���j
a)�ł͌j���Ab)�ł͍����ŁA���ꂼ�꓀�点�ăX�e�C�����C�g�A�Ƃ����V�i���I�͖����B
����̓`�F�X�ɂȂ�����A�Ȃ�͂Ȃ����Ȃ��Ǝv������A�Ȃ�ƍ�����ɋl�ނ݂������B
H=3 UltraSchachZwang
1.nPAa7-b7 + nPAb7-h7 2.nPAh7-h3 + nPAd8-d3 3.nPAd3*h3 + WEg3*h3 =
���������āAb)�ɂ�6��̑��l������Aa)�ɂ���������Ȃ����萔�̗]�l������B
�ނ��B�����������Ƃ�����̂����B
�w������B�u���i�S�j�x�i�ߑ㏫���Ёj
2003�N08��30���i�y�j
���a31�N�̏����u���B���e�͎��͂��E��@�̏Љ�A�����ՁA����̒�ՁA���ǂ̉���A�l�����̉�}�E�n��@�Ɛ��肾������B
���Ȃ݂ɋl�����̃R�[�i�[�͋�`��V��ŁA���a52�N�́u�l���]�_�@���v�ɂ܂�܂���^����Ă���B
�}���قɍs���ċA��ɌÖ{���ŁA�}���K�w�����d�q�P�x�i�݂����ȍF�V�A�G���_�[�u���C���j��100�~�Ŕ����B
�J���Ă݂�ƁA�\���̎��ɁA�}�W�b�N�y���Œ��҂̃C���X�g�ƃT�C�����������B�i���҈ȊO�̖��O�͂Ȃ��j
�T�C�������Ă�������{���Ö{���ɔ����Ă��܂��Ƃ����̂́A�ǂ����������Ȃ̂��A�܂��Ȃ�ł��ꂪ100�~�Ŕ����Ă���̂����ɂ͂킩��Ȃ��B
�Ɍ��h�h�̑�W�U�ԁi�����E�n�A�����E�l�A12��A�������g�p�AMadrasi�j
�u�Ƌ��v�Ƃ�����̓������A�㉺�Ώ̂łȂ����Ƃ���\�ƂȂ�AMadrasi���[���������l�ߏオ��B
�������蓮���Ȃ������肷��m�F�́A������Ƒ�ς�₱��������ǁA��������A�Ƃ������ƂŁA����Ȃǂ͏o�Ă��Ȃ��n���Ȏ菇���B
�����悤�ȑ_�����A�`�F�X�ł�낤�Ǝv���Ă��A������͂����Ă��̋�㉺�Ώ̂�����A���������d�g�݂͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��B
�ł���悤�ȋ�Ȃ����T���Ă݂���ADragon�Ƃ�����������B
����́A�����̗��iRook+Fers�j�ł͂Ȃ��A�i�C�g+�|�[���̐��\�����A������ƕ��ς��ȋ�B
H#4 UltraSchachZwang Madrasi
Dragon(=S+P)h6
Neutral BerolinaPawn x 3
BerolinaPawn�Ƃ����̂́A�����Ǝ��̐��\���t�]�����|�[���B���Ȃ킿�A�ʏ�̈ړ��̓i�i���O���Ɉړ����A������Ƃ��͒��i�B
�v�����[�V�����A�_�u���X�e�b�v��A���p�b�T���Ȃǂ̃��[�����A�|�[���ɏ����Ă���B
��i�̂ق��͋Ɍ�II�̃}�l�BbRg2�̔z�u���c�O�B
�w�����炳��x�i���[���q�A���~�Ёj
2003�N08��29���i���j
�}���K�`�b�N�Ƃ��������������̂Œ��ׂĂ݂���A���ۂɃ}���K������Ă���݂������B�ł��A����͂��Ȃ肢����i���Ǝv���B�l�ɂ����߂��₷���{�B
�����A���܂�ɂ��o��l���������l����Ȃ̂ŁA���݂����ȂЂ˂�����̂ɂ́A�H������Ȃ���������Ȃ��B
�������Ȃ���A���͎��́A�z���[���r�f�I�Ŋς�Ƃ��A�r���ʼn��x���~�߂āA�S�̏��������Ă��瑱�����ς�^�C�v�̏��S�҂Ȃ̂ŁA���������q���C���ɂ͋��������Ă�B
�i���̃q���C���͂��������z���[�r�f�I�Ȃ�ĊςȂ��̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����c�b�R�~�͂��Ă����j
�����̃z�[���y�[�W�̓����N�t���[�����A�ǂ�����ʂ̕��ɂ͂킩��ɂ������E���e�[�}�ɂ��Ă��邩��A���܂���͂̂��Ƃ͋C�ɂ��Ă��Ȃ��̂����ǁA���̒m��Ȃ��ԂɁA�Љ��Ă��邱�Ƃ͂���悤���B
���̂Ƃ���̓����N�t���[�����A�C�������x�̂��ƂȂ�ʂɍ\��Ȃ�����ǁB
���S�҂����炷���ɶ�((( ((;߄D�)) )))�����ق��Ă��܂��̂ł���B
�Ɍ��h�h�̑�W�T�ԁi�lj��z�u�AG�R����lj����Ă��l5������j
�lj��z�u�n�B��������G�R���ŋl�ނ͂����Ȃ�����A�������肷��菇���\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̌`�͂��Ȃ����I�Ȃ̂ŁA���̐}�������肦�Ȃ��Ƃ����킯�B
�Ƃ͂����A�ŏI��̂W�T�����V�SG�̓��ݑ�ƂȂ��āA�X�U�̒n�_���u���b�N���Ă���Ƃ����̂��A�ʔ������B
�Ƃ���ŁA���S������p�^�[���Ƃ����̂́A���������n��̓��@�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������āA
�lj��z�u�BG�R����lj����āAH#3.5 �Q�� TransmutedKings (No White King) �����B
�������A�Q���̋l�ߏオ��́A�Ⴄ�`�ɂȂ邱�ƁB
���E�Ώ̂Ȃ�Ă̂́A�������_���Ƃ���B
�Ȃ��ATransmutedKings�́A�����鋾�l�ŁA�ʂ��������������̐��\�ɂȂ郋�[���B���̃L���O�͂Ȃ��B
�ŁA�܂��A����Ȃ̂����ɂȂ�킯�B
H#3.5 2sols. TransmutedKings (No White King)
�������]�E���]�������}�͍l�����邯��ǁA����ȊO�ɂ���̂��ȁH
�w�������x�i�c�ߎq�E���厵�C���A�˓`�Е��Ɂj
2003�N08��28���i�j
���Ȃ�������Ȃ��Ă����B���̖{�̂������ł͂Ȃ�����ǁB
�ߑ㏫��10�����ɁA�挎�̑S�����̋L�����ڂ��Ă���B
�r�肳��ɂ��ƁA�J��搶�́A�u��c����Ǝᓇ����̑Βk�����������e���Ǝv���Ă܂������킩��₷�������v�������B
�܂��A�ЂƂ��ꂼ��Ƃ������Ƃ��낤�B
�l�����S�����̃��|�[�g�͋g������B�u�l�����}�j�A�̔M���āv���������B
�g������́u�قƂ�ǂ̎Q���҂�����s�\�̐��E�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����܂������A�r�肳��̍I�݂Ȏi��ƁA�����l�̓I�m�Ȕ����ɂ��A�t�F�A���[�̐��E���g�߂Ȃ��̂Ɋ������܂����B�v�ƁB
�����A���̂��Ƃ̘b�̂Ȃ��肪�A������ƕςɂȂ��Ă���C������B
�u�x�e���Ԃɂ́v�u�v���O�������i�݁v�̒i���́A�u�Βk�̎�Ȕ������v�̒i���̌�ɗ���̂ł͂Ȃ����낤���H
106�y�[�W�̈͌�E�����`�����l���̂��D�ݏ�������A30���̒ŋ��Z�i�Ƒΐ킷��Q�X�g�E���{�l������Ƃ����̂́A���̍F������̂��Ƃ��낤���H
�Ɍ��h�h�̑�W�S�ԁi�����E�n�A�����E�l�A20550��j
Vizir�͏㉺���E�ɂP�Âi�ދ�B���Ȃ݂Ƀi�i�������ɂP�Âi�ދ�́AFers�ƌĂ��B
��������A�`�F�X�v���u�����ł͔��ɒn���ȋ�ƌ�����B
�����A�`�F�X�ł́A�L���O���|�[�����A�ꍇ�ɂ���Ă͋����Q���ړ����邱�Ƃ��ł���̂��B
���āA���̍�i�́A�����Ƃ����Vizir��~���l�߂ẮA����ւ��p�Y���B
Vizir�̒��ɁA���������ēW�J����������́A���Ȃ���A���~�j�E���̒��ɏ����}�O�l�V�E���∟���������ăW�������~�������悤�Ȃ��̂��B�i�Ӗ��s���j
����Vizir�������Ƃ���ɕ~���߂āA���萔��_���Ă݂��B
���萔�Ƃ͂����Ă��A������Popeye�N��������͈͂ɗ��܂�킯�����E�E�E�ł����̂�����B
287��͏����ł�����574��B
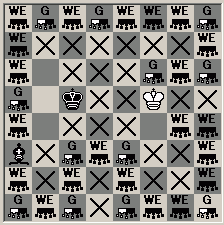
H=287 UltraSchachZwang
�~=hole
G=Neutral Grasshoppers
WE=Vizir
hole�Ƃ����̂͐i���֎~�}�X�Ńt�F�A���[��ł͂Ȃ��B���������āAGrasshopper�̔�щz���͂ł��Ȃ����Ƃɒ��ӁB
�w�h�D�[���Y�f�C�E�u�b�N ���x�i�R�j�[�E�E�B���X�A�n���J�����Ɂj
2003�N08��27���i���j
�w�z�b�g�]�[���x��94�N�ŁA�f��w�A�E�g�u���C�N�x��95�N�B�����92�N�̍�i������A���\�����͐V�N���������낤�B
�������A�����SARS�Ђ̉��ł́A�˔����`���a�̋��낵���ƁA���̉��}�I�Ή��Ȃǂɂ��āA�ǎ҂̌o���l���オ���Ă��邩��A���͂��̒������璷�Ɋ�������Ǝv���B���������A�Ɖu�w�⌌����ÂȂNJF���������P�S���I�Ȃ�Ƃ������A�^�C���g���x�����ł��関���ɂ����āA����ȂɃo�^�o�^�Ɩ��m�̕a�C�Ŏ���ł����Ȃ�Ă��Ƃ�����̂��낤���H�Ǝ��P���Ă��܂��B
�܂��������A����͎��ӓI����ɂ܂��b�Ȃ킯�ŁA��i�̖{���I�]���Ƃ͈Ⴄ�B
���̍�i�ł͋ߖ����ƂP�S���I�̗����œ����悤�ȃp�j�b�N�ɂȂ��Ă��܂��킯������ǁA��̎���̗����ɏo�Ă���l�X���A������ƑΔ䂳��Ă���B
�܂�A
�E�̂��̂����ǁA�S�R�o�Ă��Ȃ���
�E�����̉߂���I�ɏグ�ĐӔC�]�ł���l
�E�Ђ�������͂ɋC�������܂���œ|��Ă��܂��l
�E��h�����ǂ��܂ɖ��ɗ��l
�E���]�k��
�E�g�����@�Ƃ��B
���ꂪ�ʔ����̂�����ǁA�������A���̂��Ƃɂ͂����ɋC�t������A����Ȃɘb���Ђ��ς�K�v�͂Ȃ��Ǝv���B
���ʐ��S�ǂ͉H�����P����Ԃ��B���̂���������I�����I�ȏ����������B�܂��܂��悪����悤�ȋC������B
�Ɍ��h�h�̑�W�R�ԁi���E�n�A���E�l�A14��j
�{��i�W���A�����Ƃ��`���l�����Ɏ�����i�B
�ړ������̃A�N�Z���g�����邪�A���E�n�Ȃ̂Œ������͖����B
���āA��������������A���̎��E�l�Ƃ����̂́A�ȑO�����������A�`�F�X�ł��ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
WhiteUltraSchachZwang�Ƃ����̂��A�������K������𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������[���B
�܂��A�ȑO�́A����Ďg�p��SuperCirce�Ƃ�Δ䂳��������ǁA���͎�������̋�Ƃ��ĕ���������Circe������A�ނ��낻�����̂ق����A�����I�Ȃ̂�������Ȃ��B
S#8 CirceDoubleAgents WhiteUltraSchachZwang
����͂�����ƈ�{�������邯��ǁA����������Ɩʔ����̂���邱�Ƃ��ł���Ǝv���B
�w�h�D�[���Y�f�C�E�u�b�N ��x�i�R�j�[�E�E�B���X�A�n���J�����Ɂj
2003�N08��26���i�j
���y�����B���܂ň�������˂�B�Ԍ��������q�A���Ă��܂����낤�B
�ł��A�ݒ�͖ʔ������A�l���͏����Ă��邵�A�W�J���킭�킭�ł��āA���̃u�������܂��������S�ɂȂ�Ȃ��̂͂������ǁA���̕����y���{�����B
���ʐ��S�ǂ́A�H���̃S�L�Q���ɁA�J��͋�������ɏo����B
����̓A�}�`���A�ł͂��܂ɏo�Ă��邯��ǁA���l���ǂ�������̂����ڂ��B
�Ɍ��h�h�̑�W�Q�ԁi���n�A�������A�O���X�z�b�p�[�g�p�A76��j
�����̃O���X�z�b�p�[�͕s�K���Ŕ����ȓ��������邩��A�ƂĂ��l�͂ʼn𖾂��悤�Ƃ����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A��c����́A�@�B�ɗ��炸���͂ł��ׂĂ̕ω��E������`�F�b�N���A���̍�i��n�삳�ꂽ�킯�ŁA���݂����ȍ����̂Ȃ���Ƃɂ͂ƂĂ��^���ł��Ȃ����Ƃ��B
���̏�M�����̑f���炵����i�W�̌����ƂȂ��Ă���̂��Ǝv���B
���āAPopeye�N�́A����荪������̂ŁA�ǂ�Ȑ}�ł�����������ɁA����݂Ԃ��Ƀ`�F�b�N���Ă���邩��A���肪�����B
�Ⴆ�A����ȍl����̂��C���ɂȂ�悤�Ȑ}�ł��A�S�̉��������Ɍ����Ă����B
H#4* 2sols.(0.2.1.1... 2.1.1.1...)
Black royal Knight d6
White royal Grasshopper f6
White Grasshopper x 3
���̂S�̉��́A���܂����ƔՖʂ̂S�����ɕ�����Ă���邪�A 2.1.1.1.�̑g�͓������e�Ȃ̂ŁA�����R���B
�w�R�A�H�E�l�����x�i���������Y�A�����Е��Ɂj
2003�N08��25���i���j
�H���������܂߂�A���l�ܐl���e�����������̗�����B
�J��u�r�X���́A�X���O���l�������āA������Ƃ̒���Ҍ����ƂȂ����B
�����ۛ����A�����t�@���͑������A���Ƃ��ẮA�O��̖��l��ł̑Ό����A�����̓��e�͖ʔ��������̂ɁA���������͈���ɕ��Ă��܂��A�Ԑ������Ȃ������s�ǂɏI����Ă��܂����̂ŁA��蒼���̈Ӗ�����A�X���u�r�H����Ɋ��҂��Ă���B
�Ɍ��h�h�̑�W�P�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�A�p�I�A�����p�I�A�����j�g�p�A26��A������j
����̐X���u�r�J���ł����݂��̌j�����̉a�H�ɂȂ��Ă������A�����̌j�Ƃ�����́A���炭�s���R�ȋ�ł���B
���̕s���R�Ȍj�ł̋������B
��҂̓t�F�A���[�n�Ȃ�ł��邱�Ƃ��A�m���Ă��Ȃ��Ƃ������A�܂��A�t�F�A���[�n���ƁA���̂��Ƃ͂ł���B
�����|�[����������Ă݂��B
H#18 UltraSchachZwang
White royal Pawn h5
Pao a1, neutral Pao b1, neutral Pawn g5
���̂��Ƃ͂ł���Ƃ������Ă݂����A���̎d�g�݂��ƁA�E�����͂ł��邪�A�����E�͂ł��Ȃ��B�ǂ����Ă��H
�wLEONID KUBBEL��i�W�x�iYakov Vladimirov�ҁj
2003�N08��24���i���j
����܂��O���̃V���[�Y�{�ŁA�G���h�Q�[��100��B
L..Kubbel��Rinck���h���[�������B
���낢��ȃh���[�̏����iK��K+S+S�Ƃ��j��̌��ł����B
���s����̌��e�𑗂�B
�l������������̂͋v���Ԃ�B
���܂�ǂ��̂��ł����A����Ő������낦��B
����A���낢��n������݂��`�F�X�v���u�����i�݂�ȃt�F�A���[�j�̒��ŁA�o���̈����Ȃ����̂��A�C�O�����ɓ��e�B
���ꂩ����N2�炢�A����Ă݂悤���ȁB
�Ɍ��h�h�̑�W�O�ԁi�lj��z�u�B���E�X�e�C�����C�g2���n�삹��B������g�p�j
���̒�������g���āA2��̎��E�n��n�삹��A�Ƃ����̂̓V���[�Y�Z���t�i�X�e�C���j���C�g�ɋ߂��B
�V���[�Y�̏ꍇ�́A�Ֆʂɔz�u����Ă�����S#2�i���邢��S=2�j�����A�Ƃ������̂����A�lj��z�u�͂���̊g��ł��ƌ����邾�낤�B
������ŋl�߂邱�Ƃ��ł���`�͌���I�Ȃ̂ŁA������������������������킯���B
�E�E�E�ƁA���ł͂킩���Ă��Ă��A����}������Ɠ�����������Ȃ�B
���ʋ����������Ŋ����������Ȃ��̂����A�Ȃ�ł���Ȃӂ��ɔՖʂ̂R���ɂ�������J�^�`�ɂȂ�̂��H
���̍�i�W�́A�ǂ��܂ōs���Ă��A�ł������Ȃ̂��낤�B
�����܂�
Ser-H#2�@Circe�@2sols.
�wHENRI RINCK��i�W�x�iYakov Vladimirov�ҁj
2003�N08��22���i���j
20���I�����̃G���h�Q�[���P�O�O�ǁB���E���ł͂ǂ����Ă��G���h�Q�[���ŋ�킷��B�����ŃZ�I���[�̕�����Ǝv���A���X�N���́u�{�̉Ɓv�ōw�����������q�B
�T�N���t�@�C�X�ɂ��AR��Q�𗎂Ƃ��Ƃ����̂��A��i�̃e�[�}�ł��邱�Ƃ������悤�Ɋ������B���̕��A�喡�ȋC������B
����Ȃ�����d�����������ȁB
�Ɍ��h�h�̑�V�W�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�ALocust,Vao�g�p�A36��j
�����ɂ��P��Ƃ��Ă����B
���[�J�X�g�ƃ��@�I�ɂ�鑗�����ŁA������̖��͔������A�����͉��X�e�C�����C�g�ɂȂ��Ă��āA���ς�炸�I���B
������݂Ă邤���ɁA���[�J�X�g�����v�������B
������ƒP�������邯�ǁB
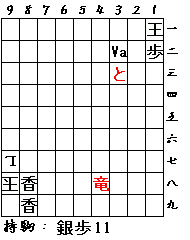
�����E�X�e�C�����C�g�@34��
13Locust, 32Vao
�w�^�C���X���b�v�����ېV�x�i�~����Y�A�u�k�Ёj
2003�N08��21���i�j
���ē�֊�ɂ������ŁA�t�W�e���r���@����Ă���B
���̂悤�ɑ��l���P�i�����ƂŁA�E�P��_�����ԑg�́A�����L�c�߂��n����Ă������ق����悢�B���l�̐l�i�d���Ȃ��s�ׂ��A�����Ɉ�������Ȃ����Ƃ������Ƃ��������Ƃɂ���āA�����w�Z�Ȃǂ̃C�W���h�~�Ɍq���邩������Ȃ��B
�Ɍ��h�h�̑�V�X�ԁi���n�A���ŕ��l�A������g�p�A�V��A�c�C���j
������ɂ�鍇��̋t���p�Ɠ���B
������͂ǂ��瑤�̎�Ԃł��A���������Ƃ��ł��邪�A�u������v�ɂȂ��Ă���Ԃ́A�u�����v�̊T�O�͂Ȃ��B
���̂��߁A�Ȃ�Ƃ�������ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̎菇���I���c�C���ɂ��Ȃ��Ă����i�����A�����������[���ŁA�u������v�Ƃ����T�O�ɂ��u�����v����������A�ǂ��Ȃ邾�낤���H
�Ƃ肠��������Ă݂�����ǁA���ʂ̃��[���ƈ�a���̂Ȃ���i�B�]�l�ނ����B
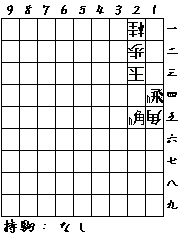
���l�T��B b)21�j->52
14������A25�����p
��������o���Ȃ��B
���u������̎�����������v���̃��[��
a) 24������A���p�A14�����p�A13�ʁA11������I�܂�5��B
b) 34�����p�A43�����p���A33�����n�A���p�A41�����p�I�܂�5��B
������Ɩʔ����̂́A�U�ߕ����������������A�Ō�܂Ŏg�킸�ɋl�߂Ă��A��]��ɂ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�l�ߏ��}�͋ʕ��̎�Ԃ�����A������͋ʕ��̎��������ł���B
���������āA������̍���ɁA���ʍ��͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
���Ă݂�ƁE�E�E����ȍ���v�����Ă��܂����B
�Ȃ�ƁA�u�I�[�����v�u�I�[�����h�h�v��̂V�A�����ł���B
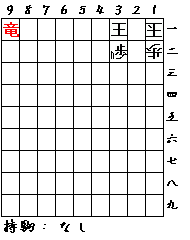
�������l�B32������
����莝����c��S���i������͂Ȃ��j�B
���u������̎�����������v���̃��[���B
32���A81�������A�����A71�������A�����A61�������A�����A51�������A�����A41�������A�����A31�������A�����A21�������A�����܂�15��l�B
�E�E�E���[���̓��������ĕ\�����Ă͂��邯�ǁA���[��[�A�z�炵�����̂ł͂Ȃ��A�����ƒm�I�ɍ�肽�����̂��B
���_���̋t���p�Ƃ����̂͂������̂ŁA�ق�̂�����ƂЂ˂��Ă݂��B�u�I�[����easy�v�Ɩ������Ă݂邩�H
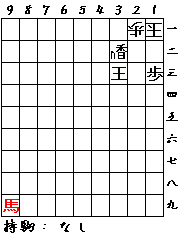
�������l�B32������
����莝����c��S���i������͂Ȃ��j�B
���u������̎�����������v���̃��[��
32���A88�������A���n�A77�������A���n�A66�������A���n�A55�������A���n�A44�������A���n�A33�������A���n�A22�������A���n�A�����A12�������܂�17��l�B
2���88�������͐�قǂ̈Ӗ��t���Ƃ͈قȂ�B
22�j���Ȃǂ��ƁA12�������Ƒł���Ă���܂ł�����A����̒�������Ֆʂɑޔ������邽�߂ɁA�����������̂ł���B
�w�����̓s�@���x�i�X�e�B�[�����E�n���^�[�A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j
2003�N08��20���i���j
���܂ЂƂ���オ��Ɍ�����B�Ƃ����̂��A�i����Ȃ��Ə����ƃl�^�o���ɂȂ邪�j�P���D�ΏƂ̎�҂������A�r�����猻��Ȃ��Ȃ邩��B
������������A���̃V���[�Y��i�ɁA�o�Ă���̂�������Ȃ�����ǁB
�ÓT�I�Ȍ�ϊ����B�i�R�W�W�y�[�W�j
�����n�т̖�A�Ƃ�킯�A���������̐����u�̎Ζʂł̖���A�ǂ�قǑ����R���Ђ낪����̂��A�ނ͂܂������킩���Ă��炸�A����ꏊ���Ȃ������B
����VS���k�͂��������������B
�����P�P��A�������ɗ͐s��������ǁA���ꂾ�����A�v���c���Ƃ���͂Ȃ����낤�B
�Ɍ��h�h�̑�V�V�ԁi�����E�n�A�����E�l�ALion�g�p�A�P�O��j
Lion�Ƃ����̂́A�N�B�[���̕����ɁA�P������щz���Ĉړ������B�u����A����v�O���X�z�b�p�[���Ƌ�����ꂽ�o��������B
��҂́uLion�ł̍��������Ă݂��������v�Ƃ����̂��n�쓮�@�Ƃ̂��ƁB
�`�F�X�ł͎��������Ďg�p���Ȃ�����A����͈ړ����������肦�Ȃ��̂ŁA�ʏ�̎�Ƃ����ĕς��Ȃ����A����̍��������Ă݂����A�Ƃ����̂́AUnder Promotion�̑n�쓮�@�ɒʂ�����̂�����Ǝv���B
�����Ƃ�����́A�u�s�����m�v�Ƃ������������邯��ǁB
���Ȃ݂ɁA���������Ďg�p���郋�[���ɋ߂����̂Ƃ��āASuperCirce�Ƃ����̂�����A����͎���������������̔C�ӂŁA�Տ�̂ǂ����ɍĐ������郋�[���B�������A�����̋�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����Ǝ���Ďg�p���[���̗ގ��́A��c������w�E����Ă���B
S#4�@Lion d8
SuperCirce
�܂��܂��̏o���Ȃ̂ŁA�ЂƂǂ����ɓ��e���Ă݂邩�ȁH
�w�����̓s�@��x�i�X�e�B�[�����E�n���^�[�A�}�K�Ѓ~�X�e���[�j
2003�N08��19���i�j
�u�����`���̓s�s�̑����������ł���悤�ɁA�s�s�Ƃ������͈̂����Ɖ��y�̌��z�ɂ���Ă̂݁A����ɂ����A���̂悤�Ȑl�Ԃ̎�_�����e����݂̂Ȃ炸���シ��قǂ̈��S���̌��z�ɂ���Ă̂݁A����������B�������̌��e�������A���ׂĂ�������̂��v�i300�y�[�W�j
�������傤����߂��A�J�W�m�����悤�ƃK���o���Ă���m���͂�����������A���̑䎌�ɓ��ӂȂ̂����B�܂��A�q���Ƃ����Ă����c�ƃ��O���Ƃ͈Ⴄ���B���邢�͂��łɈ����Ɖ��y�̌��z�ɂ���Ă��̓s�s�͑������Ă���̂��낤���H
�Ɍ��h�h�̑�V�U�ԁi���E�n�A���E�l�A�S�Q��j
���萔�̃Z���t���C�g�Ƃ����̂́A����A���ɂȂ�₷���A���̓_�A���̋l�����̎��E�l�Ƃ��������o������Ǝv���B
��c����́A���E�l�ɂ͍���������Ə����Ă���B�������A�������`�F�X�̃Z���t���C�g�ł͍���͂Ȃ��B
���̂����ɁA�ǂ����ʼn���ł͂Ȃ��u�ʂ邢�v�������ȂǂŎ菇����A�Ƃ����̂��퓹�ŁA��i�̉��s���͐[���Ȃ�̂����A�萔������̂ɂ͌����Ă��Ȃ��B
�������A���̂ق��ɂ��A�����݂����ȏ���̃o���G�[�V�������R�����Ƃ������Ƃ�����B
���X�N���̐��E���ł́AMetaxa�c�A�j�[�i�D������ƃM���V���̎��AMetaxa���Ⴆ��j�́A6��ȏ��S#n�ŁA�~�j�A�`���A�i�ȑf�}���j�A���A�l�ߏ��̌`���Q����A�Ƃ����̂��ۑ肾�����B
����͂��Ȃ茵���������i���ɁA�~�j�A�`���A�Ƃ����̂��h���j�ŁA�G���g���͏��Ȃ������悤���B
�������킵�Ă݂����A5�肪���������������B
�����P���ɋt�Z����8��ɂ��Ă݂����A�P���ȋt�Z�͂��������܂�Ӗ����Ȃ������Ǝv���B
S#8
1.Qa6+ Qa4 2.Qd3+ Qb3 3.Bc1+ Ka4 4.Bd2!
4.... Qxc2 5.Qa6+ Kb3 6.Qb5+ Ka3 7.Bb4+ Kb3 8.Sc1+ Qxc1#
4.... Ka3 5.Bb4+ Ka4 6.Qc4 Qxc2 7.Bc3+ Ka3 8.Bb2+ Qxb2#
�w�����e�����[�Y�x�i���c���i�A�x�m���t�@���^�W�A���Ɂj
2003�N08��18���i���j
���[�Y�Ƃ�����̓t�F�A���[��ɂ�����B
���̓������烍�[�Y�Ƃ����̂�����ǁA�K�N���͎l�t�̃N���[�o�[�Ɏ��Ă���Ǝv���B
H#4 2sols. UltraSchachZwang
Neutral rose h3
Neutral nightrider d4,g6
Roh6�́Ag5,h7,e6,c5,b3,c1,g1,f4,f8,f2,d3,d7�Ɉړ����邱�Ƃ��ł���B
���āA����̈�M�����̕��@�ɑ��A�C���`�L���Ƃ����ӌ������邯��ǁA���̒��x�ŃC���`�L�Ƃ͕Е��ɂ��B
�������̈�M����������ɔ��W�����āA���x�́u�ʁv����M�����ŏ������@���l�����B
�C���`�L�Ƃ����̂́A���������̂������̂��B���u�ʁv����M�����ŏ������@
�Ɍ��h�h�̑�V�T�ԁi�����E�n�A�����E�l�A�i�C�g���C�_�[�A�����i�C�g���C�_�[�g�p�A�U��A�c�C���j
����̑g������₤�^�C�v�̖��́A���R�Ȃ���A�`�F�X�ł͑z�������Ȃ��B
�������A�����悤�Ȋ����̎菇���ł��邩������Ȃ��t�F�A���[���[�����v�������B
�uJapanese Reusable Circe�v
���ꂽ��́A��������̒���̎�ԂŁA�ʏ�̒���̂����ɁA�Տ�̔C�ӂ̈ʒu�ɓG�̋�Ƃ��ĕ�������B
����ȊO�ɕ������Ȃ��ꍇ�́A��x�ƕ����ł��Ȃ��B�E�E�E�i���j
�������邩�ǂ����̑I���ƁA��������ꏊ�́A�ՖʔC�ӁB
�������A�|�[���Ɋւ��ẮA
�@�G�w�P�i�ڂɂ͕��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�A�|�[���̕����ɂ��A�����ɋl�݂ƂȂ镜���́A�s�\�B
�Ƃ�������������B
���`�ɂ����āA�u���O�Ɂ�������������ǖʁv�Ƃ����悤�ȃR�g������݂����i���l������B
�Ȃ��A�i���j���O���A�����Ɠ����Ďg�p���[���ƂȂ邯��ǁACirce�Ƃ������������Ȃ��Ȃ�B
����ō�i���ł��邩�Ȃ��H
�w�V�S�L�Q������Ԑ�@�x�i�ߓ����a�A���{�����A���j
2003�N08��17���i���j
NHK�����u���Ő����搶���A�u������M�����ŏ����ɂ͂ǂ�����悢���v�Ƃ��������o�肵�Ă����B�������͎��ɂ͂��������A���t�F�A�Ɏv�����B�m���ɂ���Ȃ�A�u��v�ł��u���v�ł���M�ŏ�����B
�������A�����v�������ʉ��̂ق����G���K���g���Ǝv���̂����B
�Ɍ��h�h�̑�V�S�ԁi�����E�n�A�����E�l�A�i�C�g�A�����i�C�g�g�p�AMadrasi�A�P�S��j
�����̓i�C�g����������A�Ȃ�Ƃ��u���b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A�W�R�ʂƂ��V�Q�ʂƂ��A�ʂ͋߂��ɒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ŏI��u���i�C�g�v�̂悤�Ȏ�ł͂��肦�Ȃ��B
���ǒ�����ŋl�߂�킯�ɂȂ�B
�ŏI��V�Q�����i�C�g�́A���Ԃł͓����邪�A���Ԃł͓����Ȃ���ɂȂ��Ă���B
���āA����͂����̂�����ǁA�`�F�X�v���u�����̌����\�t�g�ł́A�ŏI��ɑ��āA�X�R�i�C�g�Ƃ��ē���Ă���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
������{�}�h���V�̂Ƃ��̓����̉۔���ɁA�o�O������̂��낤���H
�w�����������牱������������x�i��㖲�l�A�W�p�Е��Ɂj
2003�N08��16���i�y�j
�����SolvingChess�̃y�[�W�͂�͂�Ȃ̊ԈႢ�炵���AFM�͊O����Ē�������Ă����B
���ƁA�������ł�RexMultiplex�ɂ��ẮA�v����ɁA���C��������Q�ȏ�g���Ă����i�́A���̋l�̏�������ʋl��RexMultiplex���ǂ��炩�Ȃ̂ŁA�����\�����Ă��邾���̂��ƁB������肾����A���܂�l�̏����͊W�Ȃ��̂����ǁB
�����̋C���͂Q�P�x�B�J�͌������ǁA���~�ɕ�Q�Ƃ��������͏�����̂ł͂Ȃ����B�_�Ƃ͂����ւ낤���ǁB
�A���ɍs���āu�V�S�L�Q������Ԑ�@�v����B�_�{�ԉΑ��͉J�Œ��~�炵���B
�Ɍ��h�h�̑�V�R�ԁi�lj��z�u�A����Gtrasshopper�z�u�łP��l�����j
������ŋl�߂�͓̂���B
�����Ă��̏ꍇ�A���̈ʒu�ɖ߂���Ă��܂����炾�B
Grasshopper�́A��������Ώ̂�����A��r�I���₷���n�Y�����A������P���ł������Ȃ����߁A���������ŋl�߂�Ƃ����̂́A���ɓ���B
�܂��A�P�_�ɂ����������Ȃ����Ƃ���A���܂��z�u���Ȃ��Ƌʂ̉����u���b�N�ł��Ȃ��B
���̍�i�̋l�ߏオ��̏ꍇ�A�X�T�ƂW�S��G�ʼn�������Ă���B
�X�T��G���X�R�ɒ��ԂƁA����ǂ͂X�R�ƂW�R��G�ʼn���ɂȂ�B
�܂��W�S���W�Q�ɒ��ԂƂX�P�ƂW�Q�ʼn���B
�W�S���U�Q�ɒ��Ԃ̂��T�P�ƂU�Q�ʼn���ɂȂ�B
������Ԃɂ��܂��z�u����Ă���B
���̍�i�́A�t�B�������h�ŃJ�C���[�h���Ɍ����āA�uperfectly�v�ƕ]���ꂽ�Ƃ����B
�Ƃ���ŁA�t�F�A���[��ɂ́AContraGrasshopper�Ƃ����AGrasshopper�ƑΏƓI�ȓ�������������B
����́A�אڂ�����ł����W�����v�ł����A�W�����v���Ă�����Q�݂����ɑ����ē����������������ł���A�Ƃ������́B����Ȃ炿����Ɛ��\����������A���₷�����Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��B
����������J��������ǁA�U���łł����B
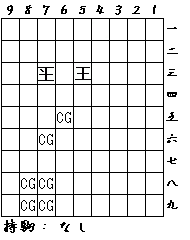
�������A�����`�F�X�Ղ�bKc6,wKe6�Ȃ�A�����Ƌ���K�v�ɂȂ�B
�`�F�X�Ղ̋��������߂Ċ������B
�w�ēY���x�i���ѐM��A�������Ёj
2003�N08��15���i���j
Solvingchess�̃y�[�W
http://www.geocities.com/solvingchess/
���݂��
47.FM K.Yamada (JAP) 2409 �ɂȂ��Ă���B
���͂�����FM�ɂȂ����̂��낤���B
�����P��Ɠ������炢�̐��т��o����FM�Ƃ����̂́A�ᓇ�搶�ɋ����Ă�������̂�����ǁB
�Ɍ��h�h�̑�V�Q�ԁi�����E�n�A�����E�l�U�S��APWC�j
PWC�Ƃ������[���́A�`�F�X�ł����\����Ă���B
�����A����A���̏ꍇ�́A�v���u�����Ƃ������l�����̕��ʍ�ɂ����Ƌ߂��Ȃ��Ă���悤�Ɋ�����B
���̍�i�ł́A���Ƃ�����̓����ɂ��A���킶��ƕ��������Ă����菇��\�����Ă��邪�A�`�F�X�̏ꍇ�͋��̂悤�Ȓn���ȋ�Ȃ����ƂƁA�Ֆʂ��������Ƃ���A�����������J��Ԃ�����ɂ͌����Ȃ��Ƃ��낪����B
�����悤�Ȏd�g�݂őn�삵�Ă݂����E�E�E
H#12.5 UltraSchachZwang PWC
1...Kc6-c5 2.Sb8-a6 + Kc5-d5 3.Sa6-b4 + Kd5-d4 4.Sb4*c2 [+wPb4] + Kd4-c4 5.Sc2-a3 + Kc4-d4 6.Sa3-b5 + Kd4-d5 7.Sb5-c7 + Kd5-c5 8.Sc7-a6 + Kc5-c6 9.Sa6*b4 [+wPa6] + Kc6-b6 10.Sb4-d5 + Kb6-b5 11.Sd5-c7 + Kb5-c5 12.Sc7*a6 [+wPc7] + Kc5-c6 13.Sa6-b8 + c7*b8=Q [+bSc7] #
��{�������ǁA���������A���`�ɊҌ����Ă͂��邩�B
�w��s�������x�i���W�����A�˓`�Ёj
2003�N08��14���i�j
���̓��L�ł̋Ɍ�II�̉��ɑ��āA�^�����烁�[���ł��ӌ������������B
�����Ƒ����Ă��邱�Ƃɔ���������Ƃ����̂͊��������肾�B
�������A��R�Ԃ̔h���ō�����������́AVizir�����ʼn��X�Ɖ��肷�邾���ŏ��`�ɖ߂��Ă��܂����Ƃ��w�E����Ĉ��R�B����݂͂��Ƃ��Ȃ��B
�܂��A���̂����ɒ��������ƁB
�Ɍ��h�h�̑�V�P�ԁi���n�A�������R�R�P�Q��A���C�������[�p�[�n�S��A�AVizir�g�p�ARex Multiplex�A������j
�ڐV�������[�p�[���S�����g���Ă��邯��ǁA�d�g�݂͂R�ԂƓ��������ɂ�钷�萔��i�B���[�p�[����v�̒��j�A���Z�j�݂����B
Rex Multiplex�Ǝ�����̈Ӗ��͂悭�킩��Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA(1,7)-���[�p�[�͈ړ��������A���[�g�T�O�ɂȂ邪�A���[�g�T�O���[�p�[�ƌĂ���Ƃ͕ʂ̋�ł���B
H#2* WhiteUltraSchachZwang
RoyalRoot50Leaper c8,e2
Set�͈ȉ��̎菇�B
1...Bd3-a6 + 2.rRFc8-b1 Ba6-d3 + 3.rRFb1-a8 Bd3-e4 #
�����āA������w���ꍇ�́A
1.rRFc8-h3! Bd3-f5 + 2.rRFh3-a2 Bf5-e6 + 3.rRFa2-h1 Be6-d5 #
�u�r�̓����v�ł��Ȃ��݂�Antelope�Ƃ�������A(3,4)-Leaper�ł��邪�A���[�g�Q�T���[�p�[�Ƃ͕ʂ̋�ł���B
�w���{�̍U�h�x�i�I�{�O�A�n���J�����Ɂj
2003�N08��13���i���j
asahi.com�����ɁA���Ԑ�ŏI����������I�[�v���̏������������Ă���B
���Ԑ�ɂ��āA�v���̕��X�Ȃǂ̈ӌ����ǂ߂āA�Ȃ��Ȃ��ʔ����B
���́A���̑nj��ʂɂ͋^��Ɏv���Ă���B
�Ȃ��Ȃ�A�b�ǂ݂Ƃ������[���́A�c������b��K�X�m�点��O��Ő�������NjK��ł���ƍl���邩�炾�B
�����炱���A�ǎ҂́u�Q�T�b����ǂ�Łv�Ƃ��u����傫�����āv�Ƃ��v���ł���B
�ɒ[�Ȃ��Ƃ������A�g�C���܂Ő����͂����炢���̃f�J���l�ɑウ�Ă��炤���Ƃ��ł���͂����B
������A�Ō�̂P�O��ǂ܂ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�F�����Ȃ��܂܂ɁA�����I�ɕ����ɂ���邱�Ƃ́A���肦�Ȃ��B����́A�ʂ��l�܂����܂ŁA�����I�ɕ����ɂ���邱�Ƃ��A���肦�Ȃ��̂Ɠ������Ƃ��B
�����Ƃ��A�ǎ҂����玞�Ԑꕉ����F�߂邩�A���邢�͕b�ǂ݂Ńg�C���ɗ��������Ƃ������Ȏ��ԉ҂��ł���Ɣ��肳�ꂽ�ꍇ�ɂ͕ʂł��邪�A���̑ǂł͂���ȍٗʂ͂Ȃ������悤�Ɏv���B
�Ɍ��h�h�̑�V�O�ԁi���n�A���l�P�R��A���C�������ʋ�g�p�ARex Multiplex�A������j
RexMultiplex�Ƃ������[���́A���ׂẴ��C�����������ɋl�݂ƂȂ��Ă���`�ɂ����Ă����Ƃ������[���B
����A��P�Ԃ̓�ʋl�́A�ǂ��炩�̃��C�������l�߂�Ώ����ł���Ƃ������A�ǂ��炩�̃��C����������`�ɂ����Ă������[���ŁA���ꂼ��قȂ�B
���Ȃ݂ɁA�́A��ʋl�̃��[���łV�X�ʋl�i�ʂ��V�X�g�p����j�Ƃ�����k��i������������ǂ��ARexMultiplex�̂ق��̍ő��́A�����Ȃ낤�H
��]��₷�����l���������Ƃ���A�X�����B
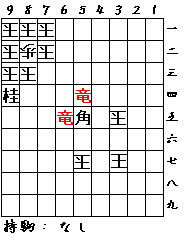
��]��Ȃ��łX���Ƃ����̂́A���肤�邾�낤���H
�`�F�X���ƂP�O���܂ʼn\�Ȃ悤�Ɏv���B
���āA�{��́A���ׂẴ��C�������l�߂�ȑO�ɁA���ׂă��C�������ʋ�ł��邩��A�ǂ̂悤�ȋ�Ȃ炻�������}�����肤�邩����z�����Ȃ���Ȃ炸�A����ɁA������ؖ�����菇�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̂������ς�炸���ʂȂƂ��낢�������i�V�ɁA�����Ɏd�オ���Ă���A�����ȍ�i�̂ЂƂ��B���̋l�ߏ��́A�Y��悤�ɂ��Y����Ȃ����낤�B
�w����g�� ���x�i�c�����A�S���{�l�����A���j
2003�N08��11���i���j
���ꂾ���̐��̑S��s���ȋl�����Ƃ����̂͂悭�����Ȃ����̂��Ɗ��S��������B
�Ō�̂ق���
�l�����p���_�C�X���A���I�S��ɒB����Ɠ��l��ƂƂȂ�A���R�o�i��������邱�ƂɂȂ�B
�Ӂ[�ށB�����Ȃ̂��B
�������A�����͂����Ă��A�{�c�ɂ���邱�Ƃ�����̂����B
����ȕ��Ȃ��Ƃ������Ă���ƁA�̐l�ɑ��ĐS�����Ƃ͂����A��i���S�ǂ̂��̍�i�W���A�������삭�炢�Ȃ̂��낤���Ȃ�Ďv���Ă��܂��̂��B
�Ɍ��h�h�̑�U�X�ԁi�����E�n�A�����E�l�P�S�O��A�����p�I�A����Rookhopper�ARook-Lion�g�p�A������j
��S�Q�Ԃ��炢�ł����\����̂ɁA�{�삭�炢�܂ł���ƁA�����肪���Ȃ��B���̍�i�W�ł��ł����G�ȃT�C�N�����Ǝv���B
�����̃z�b�p�[�n�Ɖ���A���Ƃ����̂͂���قǂ܂łɓ���̂����B
�����}�l���č���Ă݂��B
H=29 UltraSchachZwang�@NoBK
Pao x 15 , Dolphin d1, Royal Pawn e1
Dolphin�Ƃ�����́AGrasshopper+Kangaroo�@�̓���������B
1.PAc1+ nDOb1 2.PAd1+ nDOxf1 3.PAg1+ nDOh1 4.PAf1+ nDOxd1 �łP�T�C�N���B�Ō��29.DOg1+ Bxg1= �܂ŁB
�w����x�i���c�K�O�A�T���P�C�h���}�u�b�N�X�j
2003�N08��10���i���j
���X�N�����Ȃɂ��ŁA�T���F���ɗ��A��B
�䕗�P�O���̉e�����S�z���ꂽ���A�F����ԉΑ��������J�Â��ꂽ�B
�Ɍ��h�h�̑�U�W�ԁi�����E�n�A�����E�l�U��A������g�p�AHorizontal Cylinder�j
�o���ʂł��܂��܂Ƃ܂��Ă��邯��ǁA�P���Ȃ̂ŕ��ʂ̍�i�Ɍ�����B
�����͒�������̋l�ߏオ��ƂȂ��Ă���B������ł̉���́A���O�̌`�ɖ߂���Ď��邱�Ƃ������B
�����ł͐��邱�Ƃɂ���Đ��\��ω������邱�Ƃɂ��A������ɂ��l�ߏオ������������Ă���킯���B
�`�F�X�v���u�����ł́A����̓|�[���ɂ���������Ă��Ȃ�����A���܂肱���������Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���B
�w�`�����~���r�p�}���{���u ���~���r�p�}���{���u�{���~�{���������x
2003�N08��09���i�y�j
���E���ł͊e�����c�A�j�[�Ȃ�n��R���e�X�g���J�Â����B
���߂ĎQ�������e���A�r�u���ł����V�m�o�^���E�c�A�j�[�Ƃ����̂�����A�����ł�����������i������ɂȂ����B
���̍�i�́A�o�c�a�ihttp://www.softdecc.com/pdb/index.pdb�j�Ō����ł��邪�A�Ȃ��m��S���o�m�t���Ɏ�������Ă���݂������B
����ȉ��ō���̑��̐܂ɂ�����������i�W�B���V�m�o�^���E�c�A�j�[�ł̉ۑ�Ɠ����e�[�}�̍�i������������^����Ă���B
�����A�����ЂƂ�����������ŁA��H�v�ق����Ȃ��Ƃ����̂����Ȃ��Ȃ��B
�Ɍ��h�h�̑�U�V�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�P�S�O��A�����p�I�A�������C�I���g�p�A������j
������n�K���Ƃ����X�e�C�����C�g�̃p�^�[���́A�Ďg�p��������鏫�����[���̓����Ƃ����邾�낤�B
�����`�F�X�ł��Ȃ�H���[��B
H=23 Locust a6, UltraSchachZwang, Kmadrasi
������ƂЂǂ��o���B
�w�Ԃ�������ς��x�i��ĊC�A�n���������Ɂj
2003�N08��08���i���j
���E���ɍs�������ʂ��A�t�H���_�ɂ܂Ƃ߂Đ������Ă���B���N�����X�N���ł̋L�^��A�B�����ʐ^�Ȃǂ��܂Ƃ߂Ă��āA�悤�₭�ł����B
����Ȃ��Ƃ��Ă���ƁA���Ԃ������炠���Ă�����Ȃ��B
���݂̂Ƃ���A
�E�z�[���y�[�W�̍X�V
�@�i���[�V���A�ȋl�AWCCC�Ȃǁj
�E�v���p���ւ�WCCC��
�E�v���p���̌��ʍe
�E�v���p���̍�i�̓]���iW�R�[�X�x�~�ɔ����j
�E�̂�т�B�l�̏ܕi����
�ENTT�ւ̓d�b��̐U����
�E�T��l��i�W�̉p��
�E�����̐���
�E�h�C�c�֍s���Ă��܂����e�c����ւ̃Z���x�c
�E����l�����𑗕t���Ă���^�O���̕��ւ̑Ή�
�E���l���̉ۑ�쓊�e
�ȂǁA����߂ďd��Ȃ��̂�������ɂȂ��Ă���B�ǂ��������̂��B
�Ɍ��h�h�̑�U�U�ԁi������A�����E�l�S���n�삹��A�����g�p�A�c�C���j
�z�u�����ɂ������E�l�̑n��B�o���ʂ̂����E�͏]���̏����̐��E�ł��@��i�߂��Ă��邪�A���������قǂ܂łɂ������肭��Ƃ́A�N���z���������낤���B
��X�̑z�������c���̑n���́A����ɔz�u�����E�c�C�����������B
�������ꂽ�V�т̐��E�������ɂ���B
�w�痢��x�i�����\�S�A���w�ٕ��Ɂj
2003�N08��07���i�j
�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�̉e�����Ă���C������B
�����A���f���Șb�̗���Ȃ̂Ő^���͂��������ł��邵�A�ǂ�ł�Ԃ����Ȃ�����ǁA����Ȃ�Ɋy���߂��B
���ʐ��R�ǂ͒J��R�A���B
�Ō�H���Ɏ�Ԃ����A���������邩�Ǝv�������A�ǂ��Ȃ̂��낤�H
�Ɍ��h�h�̑�U�T�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�A�S�U��A�i�C�g�AGrasshopper�g�p�A������j
�`�F�X�̃i�C�g�͕��ʂQ��������A����i�C�g�Q�P���Ƃ����̂́A�j�n���Q�P�������Ă���݂����Ȃ��́B
�X�e�C�����C�g�Ȃ̂Ŏ̂Ă܂�����Ȃ��A�^�������������S�����łW����̍�i���v���N��������B
�������A���̍�i�́A����Ȑ����܂����̂��̂ł͂Ȃ��B
�����Ɠ䂪�p�ӂ���Ă���̂��B
�R�P��ڂ̂V�V�j�B���̎�͂P�V��ڂɂ������蒵�˂Ă��܂������ɂȂ�B�������A�P�V��ڂɒ��˂�ƁA�����ŁA�ȉ��W�U�i�C�g�A�W�S�i�C�g�E�E�E�Ǝ̂ĂĂ����ƁA���傤�ǂT�V�i�C�g�A�����ł͌����ďI���Ȃ��Ȃ�̂��B
�����łP�V��ڂ͂T�V�i�C�g�ŋt��]�B
��҂͏����i�Ə����Ă��邪�A���̏��͒m�I�ȏ��ł���ƌ����悤�B
���������m�I�ɏ����i�����͍̂�҂̌����Ƃ����ϓ���B
���������E�X�e�C�����C�g������Ă݂�ƁE�E�E
H=16 UltraSchachZwang
RookHopper a3, Kangaroo a2
1.RHa3-a1 + Ra4*b4 2.RHa1-a3 + Rb4-a4 3.RHa3-a1 + Ra4*c4 4.RHa1-a3 + Rc4-a4 5.RHa3-a1 + Ra4*d4 6.RHa1-a3 + Rd4-a4 7.RHa3-a1 + Ra4*e4 8.RHa1-a3 + Re4-a4
9.RHa3-a1 + Ra4*f4 10.RHa1-a3 + Rf4-a4 11.RHa3-a1 + Ra4*g4 12.RHa1-a3 + Rg4-a4 13.RHa3-a1 + Ra4*h4 14.RHa1-a3 + Rh4-a4 15.RHa3-a1 + Ra4*a2 16.RHa1-a3 + Ra2*a3 =
�w�֍s�����̂قƂ�@�P�x�i���c���A�������_�V�Ёj
2003�N08��06���i���j
���ʐ��R�ǂ͑�����ԂȂ̂����ǁA�����Z�u�r�T�؈ʎ��Ƃ����ς���������B
��̑O���ׂāA�^�C�g����ł̑���q�Ƃ����͖̂{���ɋH�ɂȂ��Ă��Ă���B
����ł͒����A�Ē��A�����Ƃ������ӂ�̌o�����ʗp���Ȃ��̂��d���Ȃ����낤�Ǝv���B
���ʐ�Ƃ����A��P�ǂ̎���L���������E�X�����Ɍf�ڂ���Ă�������ǁA��̎ᓇ�搶�w�E�̂U�Q�p�͉������Ă��Ȃ������B
���̎�͂ǂ����ŗz�̖ڂ��݂邱�Ƃ�����̂��ȁH
�Ɍ��h�h�̑�U�S�ԁi�����E�n�A�����E�l�A�P�S��A�i�C�g�g�p�A�c�C���j
�i�C�g�͂��̍�i�W�Ŏg�p����Ă���B��̃`�F�X��B���̃i�C�g��F�}�̂����E�l�B
�i�C�g�̈ʒu���V�Q�ƂV�U�ɂ��邱�ƂŁA�����^�C�v�̋l�ߏオ����Q�ʂ蓾���邪�A������A�㉺�ł���Ă���Ƃ������ƁB
�i�C�g�ɂȂ�邽�߂ɍ�����Ƃ̂��ƂŁA�K����ۂ������B
����ł��Y��ɂ܂Ƃ܂��Ă���Ǝv���B
���Ȃ݂ɁA�����E�l�̓`�F�X�v���u�����ł�����B
UltraSchachZwang�Ƃ������[���Ńw���v���C�g���������B
���߂��ɂ���Ă݂�ƁA����Ȋ����B
H#3 UltraSchachZwang 2sols.
1.Qa8-d5 + Kc4-c3 2.Qd5-d2 + Kc3-c4 3.Qd2-a2 + Re2*a2 #
1.Qa8-g8 + Re2-e6 2.Qg8-c8 + Re6-c6 3.Qc8-a6 + Rc6*a6 #
��҂́A�u��ɑ啪���ꂽ���A�v���Ԃ�ɋl����������Ă݂�ƁA�j�Ƃ�����t�F�A���[��Ɋ������āA���ȋC���������v�Ə����Ă��邪�A����Ɠ����悤�Ȃ��Ƃ�X���v�������Ă����悤�ȋC������B
�w��p�T��\�����S�W�@��̊��x�i�A��ȕv�A�u�k�Е��Ɂj
2003�N08��05���i�j
������̒���Ҍ����́A�������i�̔S������̂Ƃ������A�n�ӌܒi�̉����B
����ʼnH���u�r�n�ӑΌ����A�{�i�I�Ɏ�������B
������������A���ꂪ�A���Ă̑�R�~�����A�J��~�H���݂����ȁA���X�Ƒ����i�����́j�Ό��Ƃ������̂ɂȂ�̂�������Ȃ��B
�Ɍ��h�h�̑�U�R�ԁi�A���n�A�A�����E�l�A�Q�V�{�P��A���ʋ�A�k�����������g�p�j
���ɓ����i�ł͂��邯��ǁA���`�ŁA���ʋ���������Ƃ��k�����������Ȃ�Ȃ��`�Ƃ������ƂɋC�t����҂̑_���͂킩��B
���������ꂩ�炪��ς��B�k�����������ł��邱�Ƃ��ؖ�����ɂ́A���̂��ׂĂ̋�̗����ɋʂ��ړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�k�����������̑��ɐڋ߂���ɂ́A����Ȃ��悤�ɔ������ԂŎx���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA�X�T��A�X�R�ʁA�X�P�ʁi�T�T�u���n�A�p�j�A�Ƃ��łT�T���p�ȊO�ɂ��Ă����ĂX�V���k�����Əؖ����Ă���A�V�R�Ƃ��Ă��A����͋l�܂���Ă̓�����I���ł��邩��A���s�ƂȂ�B���������āA���͂����������A�����[���œ���̋�ł��邱�Ƃ��ؖ�������̏ꍇ�A���⍁�Ƃ����������ɂ�����Ɠ�����������������ł��邱�Ƃ��ؖ����邱�Ƃ͓���B�k���͕��⍁�Ƃ͂܂��������\���قȂ邩�炱���A���������菇����������̂��B�܂������I���B
�w�u���b�N�E�e�B�[�x�i�R�{�����A�p�앶�Ɂj
2003�N08��04���i���j
�S�l�A�̂g�o�@http://ztrhome.cside.com/�@�ɁA�S�����̕��ڂ��Ă���B
�����ɁA��c����Ǝᓇ�搶�̑Βk�ɂ��āA�u�b�̂S���������ł��Ȃ������v�Ə�����Ă���B
�ǂ����Ă��낤�B���̎��́A�t�F�A���[��`�F�X�v���u������m��Ȃ��l�ɂ��킩��悤�ɁA����������Đ������Ă����̂ɁB
�܂��A���������͓`���l�����ɂ����钷�ҕ���̌��ЂŁA��w�@�̒S����Ŏ��܂̑I�l�ψ�������Ă�����ł���A�u�Ɍ��h�h�v�ɂ͂R�O���肾�Ƃ������Ƃ��̍�i�����낲�낵�Ă��邩��A��ʐl���������͂���͂����B
�Ȃ̂ɁA�b�̂S���������ł��Ȃ��Ƃ����̂́A�ǂ��������Ƃ��낤���B
�Βk�̒��ŁA��c����̍�i���C�O�̈ꗬ�v���u���~�X�g���^����������̓J�b�g���āA��l�̌����ȑ䎌���A�킴�킴�l�K�e�B�u�ȗ���Ƃ��Ĉ����������Ă��邠����A�Ӑ}�I�ɔw�������Ă���̂ł͂Ȃ����H�Ƃ܂ŁA���肽���Ȃ�̂��B
�Ɍ��h�h�̑�U�Q�ԁi�����E�n�A�����E�X�e�C�����C�g�A�W�U��A�o�����A�Ύg�p�A����o���Ȃ��j
����A���Ƃ������[���̏ꍇ�A�o�����قǎ̂Ăɂ�����͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�o�����ɂ�鉤��́A�K���ʂ��痣�ꂽ�Ƃ��납�炩������̂ŁA�u���ʁv�����肦�Ȃ����炾�B
�Ƃ����킯�ŁA�ʕ��̋�Ɏ���Ă��炤�K�v������B���̍�i�̏ꍇ�͒[�̍��𗘗p���Ă���B����菇���͓̂`���l�������B
��������ƂɁA�[���[���`���l����������Ȃ����̂��v�������B
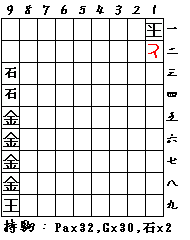
�����E�X�e�C�����C�g�B�P�Q�W��B
�o�����o�����A�f���f���������������������A��(0,0)-leaper
�w�E�l�̋�x�i���ؓ~�F�A�p�앶�Ɂj
2003�N08��01���i���j
���łɑ啔���̃v���O�����͏I����Ă���A�����͂Ђ�����ό��A���h���y�Y�T���B
�������A�`�F�X�{�Ȃ͂��łɊm�ۂ��Ă���킯�����B
�[���Ƀo���P�b�g������A��x���܂Ő���オ��B
�ȏ�ō��N��WCCC�͏I���B
�܂Ƃ߂Ă݂�ƁA����͈ȉ��̂Ƃ���B
���̕�
�E�`�[���͂U�ʂƑ���i�B���ƂP������Ă���R�ʂ������B
�E��l�Ƃ��ō����сB
�E���͂����P�ꂭ�炢�̍D���т����AFM�i�t�F�f�����}�X�^�[�j�̎��i��炵���B
�E��l�Ƃ��\���r���O�E�V���E�ɏo��B�ᓇ�搶�Q�ʁB
���n��̕�
�E����Quick�łP�O�ʁAURAL�c�A�j�[�łS�ʁB
�E�ᓇ�搶��Becherovka�łQ�ʁB
�EJapaneseSakeTourney�̓J�C���[�h���P�ʁB���͂��܂����B
�����̑�
�E���V�A�֍s���r�U�͂���ɂ����B
�E�A�G���t���[�g�͈ӊO�Ƃ܂Ƃ��B
�E���V�A�̃^�N�V�[�͈ӊO�Ƃ܂Ƃ��B
�E�z�e���̕����͍��B
�E���V�A�͏����B
�E���m�͈����B
�E���g���͕֗��B
�E�r�[���͂��������Ȃ��B
�E��������n�łقƂ�ǂ������g��Ȃ������B
�E����͂P�O���ɃM���V�A�̃N���^���ł���̂��������B
���Ȃ݂ɁA�V���R�O���`�W���P���܂ł̖{�́A�W���Q���ɂ܂Ƃ߂ēǂ��́B
���̓��L���܂Ƃ߂ĂȂ̂��B
�Ɍ��h�h�̑�U�P�ԁi�A���n�A�A�����E�X�e�C�����C�g�A�P�Q�{�P��A����Non-Stop Equihopper�g�p�j
���������āA�]�����킩��Ȃ���i�B�����A�����������Ă����ł菇�ɂ��Ă���Ƃ���A�܂��A�P�x���̉������āA�܂����Ƃ̈ʒu�ɖ߂��Ă��邠���肪�A��҂炵���Ȃ��Ǝv���B
���̃��[���Ń`�F�X�ō���Ă݂悤�Ǝv�������A�����ŏI�`�͂W���W�ł͂ł��Ȃ��B
�܂��܂˂��Ă݂����ǁA���̒��x�B
Ser-S=8
Non Stop Equihopper b8
�z�[���ւ��ǂ�