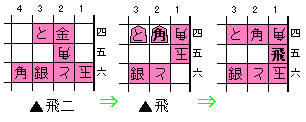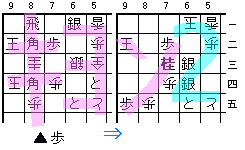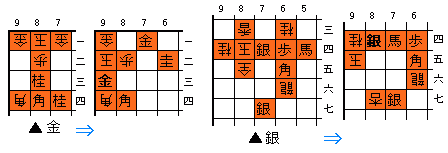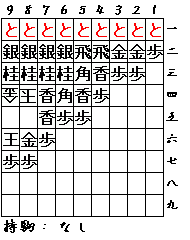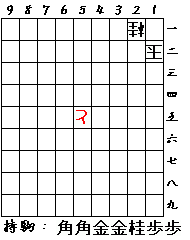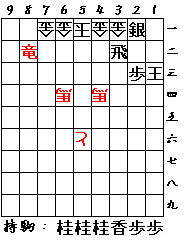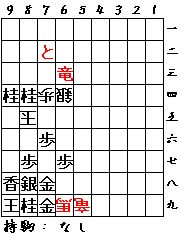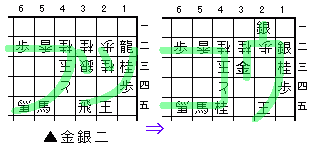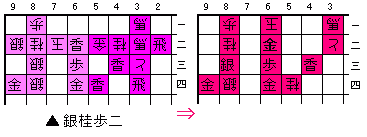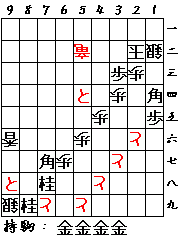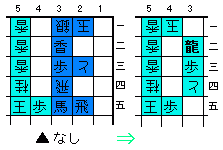�w�A�W�A�̊ݕӁx�i�g�}�X�E�l�E�f�B�b�V���A�������s��j
2005�N01��31���i���j
����Z�I�̃j���[�E�E�F�[���r�e�B�ᓇ���ҁB
�Ƃ������ƂȂ��ǁA���[�ށB���ЂƂ킩������̂������Ȃ��B
���Ȃ����e�B���E�o�[�g���Łw���̘f���x���ς����Ƃ������āA�w�ƃ��̘f���x�̓I�`��\�z�ł������ǁA����x���������Ȃ��Ȃ��i�āA����͌�ǂ��j�B
�܂��A�ᓇ�搶��̘b�Ɂu���Ȃ�����������܂��g������l���邾���̎��Ԃ͂������v�Ƃ����\�����������̂͋l������Ƃ炵���A�Ƃ������B�i�������������z���l������Ƃ炵���j
�������l���Q�ǂ͐�t�O�i�������^�C�ɁB���ׂ������ł́A���Ղ̊p�̊���ŗ����͂݁A���̂܂܉��������Ƃ��������B
�����u�r��t�͂���łP�W���P�Q�s�������ŁA�ӊO�ɝh�R���Ă���Ȃ��A�Ƃ����C������B
���͋��ɂ��Ă���̂����B
�w�I���W�M�����x�Ƃ������s�����Ƃ̒�����������R�P���ߑO�}���Ƃ̂��ƁB
���N�S�Q�Ƃ̂��ƂŁA���܂�ɂ���������B�����Ƃ��I���W�M�����ɂƂ��ĂS�Q�͖�N�Ȃ̂����B
���͎��̍�i�����܂�ǂ�ł��Ȃ��̂����A���o�V���ɘA�ڂ���Ă������q�ے��̃}���K�͖ʔ��������B�����̉�Ђ̐�`�p�C���X�g�������Ă������������Ƃ�����B���������F���āA�w���c�R�x�l���B�V��l�B
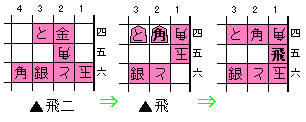
�w�Q�O�X�X �i�T�j�����g�_�E���x�i�W�����E�s�[���A�Ёj
2005�N01��30���i���j
NHK�t�͓c�������E�@�������k�������r�ŁB
���܂�ɂ������I������̂ŁA���z��̍ŏ��ɁA��t�������A�u27���قǎ��Ԃ��������܂��̂Łv���A���ΐ������������ɔ������Ă����B
��ʃ��J�̏�����قɕ����A�����搶�́w�}���S�ԁx�ƏT���������w���B
�܂��ǂ�łȂ����A���Ȃ��Ƃ����̐}���S�Ԃ́A�v�����m���o������i�W�̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��l�i���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
�T�������ɂ��P�y�[�W�����Đ�`����Ă���B
�����œ����搶�́A�u�}���v�Ɓu�l�����v�̈Ⴂ�ɂ��āA
���҂͂ǂ��Ⴄ���B�}���������l���������A����ɂ͗��j�I�ȍ���Ǝ���̎҂ɕ�����Ƃ��������B�{���́A���ɂƂ��Ď���̑��݂ł���Ŏ��Ɍ��シ��Ƃ����Ӗ���������G�z��������݂����̌��t���g�킹�Ă��炤���Ƃɂ����B
���[�ށB�v����ɁA�Õ��ȍ�i���̐l�ɕ�����ΐ}���Ƃ�����ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B
�Ƃ���ŁA���������ł́A�Ŏ��ɕ�����Ƃ������A����勴�@�j�ɕ�����A�Ƃ������ق����s���Ƃ���悤�ȁA����`�ō\�z���ۂ��Ȃ����̂������悤�Ɏv�����B
�T�������́u�}���S�ԁv�̋L���ׂ̗�͉Y�쎵�i�Ƌl�������[�^���[�ŁA���Ȃ��炱�̌��J���́A�T�������Ȃ�ʏT���l�������A�Ƃ��v�킹��B
���̂ق��A���̍��ɂ́u�l�����I�茠�v�̂��m�点���ڂ��Ă���B
���N�̑I�茠�͐�`�����������悭�o�Ă���悤�Ɏv���B
�����A�Ȃ��������ł��A�u�o��F���ѕq���A�R�c�N���A�ᓇ���v�ɂȂ��Ă���B
��c�����Y��i����
�w���n���x�i���{����Y�A�S���{�l�����A���j
2005�N01��29���i�y�j
�u�s���̉��{�v�̍�i�W�B
��i�̔z�����A�u�s����P�ԁi���ԁj�v�Ə����Ă����āA����ł͑��Ԗڂɔz�u����Ă���Ƃ����ςȑ̍فB
�܂�����͂Ƃ������A�s���̍\�z����A�悭���܂�����Ȃɂ��낢��ƁA���������ɏ�肭�n�����̂��Ȃ��Ǝv���B
�Ƃ肠�����ЂƂƂ������Ă���̂ŁA�ŕ��l���݂̕s���̍\�z���n�낤�Ƃ������́A����̓`�F�b�N���Ă������ق��������Ǝv���B
�L�����L�����F�l��璩�A�肾�����I�c�ڐG����
http://news.fs.biglobe.ne.jp/entertain/fj050129-320050129012.html
�[�������Ɛg�����Ȃ̂������ŁB�B�B�u�L�����Q�i�L�����L�����j�v�l�ł��n���Ă݂邩�ȁB
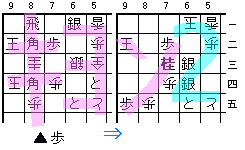
�S=����A�\=���j�B�P�T��l�B
�������A�ߌ�P���߂��Ȃ璩�A��Ƃ����قǂł��Ȃ��Ǝv�����ǁB
���Ȃ݂Ɏ��������͗F�l��ň���ŋA��͏I�d���Ȃ��Ȃ����B���R�ߌ�P���߂��B���̒�`�Ȃ�A�������A�肾�Ȃ��B
�O�̂��ߏ����Ă����ƁA�F�l��Ƃ����Ă��A�������Ă����قǐV�����\����ꂽ�F�l��̉ƒ�K��Ȃ̂ŁA�ʂɓƐg�������[�������Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������炸�B
�f���Ŏw�E���ꂽ���Ƃ����A��̌����͎��̊��Ⴂ�������悤���B���������ߌ�1�����ߑO1���ƍ������Ă����B�܂��ʔ����̂ł��̂܂܂ɂ��Ă����B
�w�����e��������x�i�L����L���A�J�b�p�m�x���X�j
2005�N01��28���i���j
�������̍D�яW�B�����Ƃ͂����Ԃ̂��ς�����Ȃ��A�Ǝv�����B�y���Ȋ��قƏ����̌��������W�J���ȃg���b�N�͑��ς�炸�Ň�d(��ͥ)��!!
�C�V��ږ�͂����Ƃ����܂Ɏ��C�ł����B�Ō�̍Ō�܂Ń_���_���Ȍo�c�҂̌��{�ł����ȁB����̂����ɋl������n���Ă����Ă悩�����B
�����Ƃ����܂Ƃ����A�������R�ǂ͌ߌ�R���S�T���ɏI�ǂƂ̂��ƁB
���[�ށB�������ɐX�����l�͐�s���Ȃ�ł��傤�ȁB
��Q��l�����I�茠�̋L���������̃T�C�g�ɍڂ��Ă����̂��A���܂��猩�����B
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/shougi/news/20050121ddm010040141000c.html
�������A�Ȃ^�C�g���́A�u�R���U���A�����s�k��̑����قŁc�v�Ƃ����͂����肵�Ȃ����̂��B�Ȃ�ŁH
�܂�����͂������ǁA�u�o��҂͏��ѕq���A�R�c�N���A�ᓇ���̂R���v���āB
��c�����Y���Ȃ��������I
�w��X���̃G���g���s�[�x�i�_���E�V�����Y�A�͏o���[�V�Ёj
2005�N01��27���i�j
�w�E�C�̃`�F�X�E�Q�[���x�̃_���E�V�����Y�̒Z�ҏW�B
����A����ǂ��Ƃ����`�Ƃ�����i�����������A����́A�w�d���̉��@�h���L�����ҁx�i�e�n�G�s�ďC�A�|���[���Ɂj�Ɏ��^����Ă����i�������B
�Ƃ���ŁA�Ō�́w�o���R�N�Ɏ����x��ǂ�ł���A��������Ƃ���[�B
���E���̒��������̎ʐ^�@���!?(* �� )~~~
����ɂ��Ă��A���̖{�A�\���͂���Ȃɂق̂ڂ̂Ƃ��Ă���̂ɁA�����̓O���Ɏ����O���ň��R�Ƃ������邱�Ɛ��������ł���B
�������A���R�Ƃ�������Ƃ����A����ς肱��ł��ȁB
�C�V�A�m�g�j�ږ�Ɂ��������ǒ��͏o�c�������E����s
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050127-00000317-jij-soci
���������A�ސE�����o�邱�Ƃ��珎���͔[�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂ɁA���̎�]�w����������ɏA�C�Ƃ͂˂��B
�܂��A�Ȃ�Ƃ������A���݂̋t���ɑς��āA�ږ�A�C�Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ������������̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�A�C�j���ɋl�����ł������Ă݂邩�B
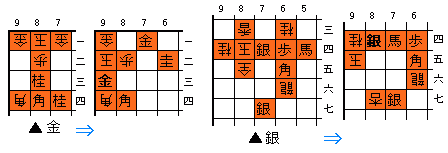
�\�����j�A�S������
�ǂ����܂��B�l�����Ɠ������Ƃ��ƂƋl�܂���Ă��������ȁB
�w���㒆�����w�I�W�W�@����x�i���ԕ��Ɂj
2005�N01��26���i���j
����������v��̒����őf�p���܂��߂ɐ�����N��`�����b�B
���̂����̍ŏ��́w�`�����s�I���x�̌���͂Ȃ�Ɓw�����x�B
���������̎��͂̂���N�̂��b�ł���B
�����D���łȂ��Ȃ��̘r�O�ƕ]���̔ނ͂���Ƃ��A�n���̖����m���Љ�Ă�������Ƃ���A���̊��m�͔ނɉ�ƈ��A�����������ɑv��̋l�������o�肵���B
�����ނ����炷��������̂Ŋ��m�͂т����肵�āA��q�ɂȂ�Ȃ����ƗU���ƁA
�u�搶�͂�����������̂ł����v�O�b�Ƃ܂��Ă��̊��m�́u�܂����v�i��Ȃ��j�u�ł͂ڂ������Ȃ��̒�q�ɂȂ邢���͂���܂���ˁB�v
�܂��A�����Ƃ��Șb�ł͂��邪�A���̑ԓx���u�����Ƃ������̒m���v�ƕ]���ꂽ��ŁA���ǐ��n�肪���܂��Ȃ��B
��������ł��ނ͏����ɁA�������i���A������̓��ґ���ɂX�ʎw��������Ă̂��A���鋫�n�ɂ�����B
�l�͂Ȃ�̂��߂ɐ�����̂��A�Ƃ�����肾�B
���[�ށB
�܂��߂Șb�B
�����w���Ƃ����A�₭���E�����Ԃ�E���y�҂Ƃ��������x�����\������{�ł́A���������b�͂��܂�Ȃ��Ȃ��B
�Ƃ���ŁA���������̎c�ǂƂ����̂́A�Ȃ��ł͂Ȃ��B�����A�L���O�������Ȃ��Ƃ�����̂ŁA���܂肷�����̂͂Ȃ������B
����̌f���ɁA���[�}�j�A���̌��ʂ��\���Ă����B
����ɂ��ƁA
1.Eric Huber 52,5
2.Vlaicu Crisan 48,5
�Ƃ̂��ƁB���[�ށB���E�̃��x���͍��������B
�w�ӂ肾���ɖ߂�@���x�i�W���b�N�E�t�B�j�C�A�p�앶�Ɂj
2005�N01��25���i�j
���ԗ��s�e�[�}�̂r�e�����A���ԗ��s�̌������Ȃ�Ƃ����[�����X�Ƃ������A����y�Ƃ������B
��ɂ���čs����ł��낢�����������Ƃ������オ���āE�E�E�Ƃ����W�J�B�܂��܂����B
���s����̂Q�����̌��e�𑗕t�B
�Ȃ�����ƐV���ɂ͐h���̂������Ă���悤�ȋC�����邪�A�܂��������B
23���̃\���r���O��R���e�X�g�̃t�����X�̌��ʂ��A�R���g���[���[�̃J�C���[�h���ɂ��A�ȉ���BBS�ɕ���Ă���B
France Echecs http://www.france-echecs.com/index.php?mode=showComment&art=20050123225331810
�����A�����_�ŋg���N�̓��_�͐��E��Q�ʃ^�C���B
���ɂ��Ă̋c�_���Ȃ���Ă���̂ŁA���Q�l�B�i�t�����X�ꂾ���ǁj
�w�ӂ肾���ɖ߂�@��x�i�W���b�N�E�t�B�j�C�A�p�앶�Ɂj
2005�N01��24���i���j
���{�N���̍�i��ChessBase�Ō���(A='Hashimoto' �Ɠ��͂��Č�������悢�j����ƁA61��q�b�g�����B
���[�ށB�������B
�Ȃ��ɂ́A��������Ă������������̂��܂܂��B
�����A���ꁫ�͂܂������ĂȂ������悤�ȁB
Satoshi Hashimoto
Phenix 2000
SPG in 20.�@�@(14+14)
����ς�������{�����u���ꂪ�Ȃ�Ńv���C�Y�ɂȂ��̂��`�v�ƁA�Q���Ă������A�P�Ɏ�҂̔��\���܂��Ȃ����Ȃ̂������ȁB
�܂��A�v���C�Y�͌ł����낤�B�X�y�V�������P�����D���Ƃ����̂͒m��Ȃ����ǁB
�w�����d���Y�̑哹�l����70�N�x�i�����d���Y�A�k�C�������A���j
2005�N01��23���i���j
���̖{�́A�哹�l�����̖ʔ����Ƃ������A��҂̑哹�l�����ɂ�����镶�͂��y�����ǂ߂��B
�哹�l�������̂́A����Ȃɖʔ����̂͂Ȃ������悤�Ɏv���B�����A97��̑哹���ɂ͋������ꂽ�B�i�����O���A����12�N���\��j
��P�ۃ\���r���O�E�R���e�X�g����c��̎Y�Ɖ��PIO�ŊJ�Â��ꂽ�B
����́A���N���E���Ȃǂōs���Ă���`�F�X�E�v���u�����̃\���r���O���Z���A���E�Q�T�J�������ŊJ�Â���Ƃ������s�I���ŁA���{�ɋ��Ȃ���ɂ��āA�����̎��͂𐢊E�Ɣ�r�ł���Ƃ����A��L�ȃC�x���g�Ȃ̂ł���B
�i�b�o�r�Ƃi�b�`�Ƃ̋����J�ÂŁA�n�����������ɂȂ��Ă����B�R���g���[���́A�ᓇ�搶�ƁA���{�i�b�o�r��ƁA���B
�o��́A2���ԂŁA#2,#3,#n,study,S#n,H#n 6��B���ꂪ�ߑO�ƌߌ��2��s���A12��ʼn��������Ǝ��Ԃ������B
����Ȃ߂��Ⴍ����ȓ��͂Ȃ������悤�Ɏv�����A�̓_���鑤�Ƃ��ẮA���C�����C�����͂����肵�Ȃ��̂��������悤�Ɏv���B
�܂�����͂Ƃ������A���Z�Q���҂͂P�R���I�I�ƁA�v���Ă�����葽���Ɗ������B���{�̉��Z�́A���コ��Ȃ�i�W���A���҂ł���Ǝv���B
���т́A�v���p���t�R�[�X�i�t�͂t�������̗��j�S���̓��{�v���u�����E���҂̐��A�g���N��2�ʈȉ������������čD���тŗD���B
2�ʂ͐^�玁�A3�ʂ͉ԓc���ƂȂ����B
�i���M�������[�B����F�n��JCA��̈��A�B���Ɏᓇ�搶�B�E�さ�����F���̖͗l�B�E���F�����P�ʂɋP�����g���N�B)
����̑ł��グ�ł́A��������ł������������{����A�����Ƀ��g���̖����o�肵�A������s��������ꓖ����ʼn����A�Ƃ������W�J�B
�ǂ����ނ��Ⴍ����ȃe�[�}�i��i�ڂ̂��ׂĂ̋�̃X�C�b�`�o�b�N�Ƃ��j��������Ⴄ�낤�A�Ƃ���������A����ς肻�ꂾ������ŁA��������炸�Ƃ�ł��Ȃ��l���Ȃ��B
�w���݂Ƃڂ��̉�ꂽ���E�x�i�����ېV�A�u�k�Ёj
2005�N01��22���i�y�j
������������Ă���ɂ́A�W�J���x���Ƃ����A���܂莄�̍D�݂ł͂Ȃ��W�J�ŁA�������������肵�Ȃ��̂�����ǁA���̃~�X�e���̓��ِ��́A�o��l���̔����ȏオ������m���Ă���Ƃ���ɂ���B
�i�����������j
��i���ł��A����Ȋ����̖ⓚ������i�����Ɠ����ł͂Ȃ��j�B
�u�����ň�ԋ����͂��͂ȂH�v�u����͏��悾��B�v
���͂̐��͎���ŁA�ǂ̈͂����������ǂ��������܂�A�Ƃ������Ƃ��B���[�ށB���F�A�Ƃ����Ă��܂����������ǁB
�u���ꂶ�Ⴀ�A��Ԏア�͂��͂Ȃv�u�ǂ�Ȉ͂��ł��キ�Ȃ�B����́A������������Ƃ����B�U���������u�ԂɃX�L���ł���v
�ȂǂƁB�������A����͕ʂ̃X�|�[�c�̘b�ł͂Ȃ����Ǝv���̂����B
�܂�����͂Ƃ������A�V�X�R���̎�l�����A���Ə���������Ƃ��ɁA�������ɂ킴�ƕ����Ă����邽�߂̃��[���Ƃ��āA�p�X�������A�Ƃ���������͖ʔ����B
�����Ńp�X�قǖ��p�̃��[���͂Ȃ����낤����B
�������A�����ł��A�Ƃ��ɂ̓p�X���o�����ق��������A�Ƃ������A���肦�Ȃ��͂Ȃ��B���Ƃ�����Ȃӂ��ɁB
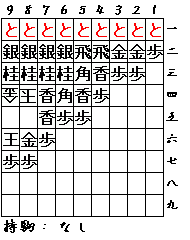
�w�v�w���q�x�i���c�N�A�V���Ёj
2005�N01��21���i���j
����҂���ɁA���N�̍���������ׂ������Ă������Ƃ��w�E�����B���[�ށB
�����ŋC������ł���X�L�ɁA�����Ɗ����Ȃ�����ア�̂��Ȃ��B
�k�����爢�{����̐V���Ɠ��l������肪�͂��B
���̉ۑ�́u21�j�z�u�v�Ȃ����ȁB
�u���}�ȉۑ�E�E�E�Ƌ����Ȃʼn��낷�悤�ł́A���͍�ƏW�c�̖��ɔ�����̂ł���B���w�́v�Ƃ��邯�ǁA���}�ł͂Ȃ��Ǝv���B
21�j�z�u�A�Ƃ����̂́A���\����B
���߂��ɂ���Ă݂����A15���54�j���������߂ɁA55�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂����B
�������A16���43�ʂ��ϓ����B
���[�ށB
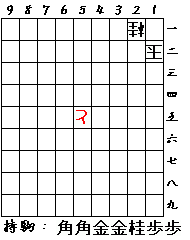
���A�u21�j������v���āE�E�E21�j�ȊO��u���Ă������̂��[�B���}�ȉۑ�A�Ƃ������A�ۑ�ȑO����Ȃ��B
�w�E�[�U�b�N���̎��́x�i�V���[���b�g�E�}�N���E�h�A�}�K�Ѓ~�X�e���[���Ɂj
2005�N01��20���i�j
����̃A�[�T�[��w�C���[�ɑ����A���̍�҂��ŋ߂��S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ���B
�̂ǂ��ȑ�w�̂���c�ɒ��ɋN����E�l�����Ƃ����A�Ȃ�Ƃ��N���X�e�B�ۂ�����N���X�e�B���ۂ��W�J���B���������͂�����ƂˁA���Ċ����B�������ǂނƈ���Ă���̂����B
�ǂ���畗�ׂ��������݂������B������ҍs�����B
�w���`�@���x�i�A�[�T�[��w�C���[�A�n���J�����Ɂj
2005�N01��19���i���j
��`�ƌ�������̊W�҂��A����قǂ܂łɂ��܂��b�ɂ���߂���̂��Ȃ��B���ׂČv�Z�����ꂽ���B�����i�Ƃ����Ă������Ǝv���B
�T�������ɂ́A���{�F�����̋L�����B
�{���ł̓~�N���R�X���X��C�I�j�[�[�V�����̌��т��������Ă��邯��ǁA�Ȃ����Љ�Ă���}��20�N�O�̎O�i�ȋl�B
����Ⴄ��ނ̍�i���Ȃ��H�ق��ɁA�Z�҂͂Ȃ������̂��Ȃ��B
���́u�r�n�r�v�́A�����łł��Ă���̂��E�����B
�X�C�b�`�o�b�N���܂ނ�����́A�������N������u�n�r�n�v�l�i11��17���̓��L���Q�Ɓj�ɁA���͋C���Ă���B
���̂͑�֕��o�R���ނɂ�����n�삵���킯�����A���̍��n�삵�����ɂ͂�����Ƌ���������B����������A�����g�������ő���ď��������߂邽�߂ɑn�����A�Ƃ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
��ւƌ����A�@�c�A�x�ꂵ�Ă܂��ȁB�j��肩���]���đ�փJ�h�ԂƂ́B
�����Ė����ɂ��D��������āB�B�B�܂��A�ؗj�ł����ǁH
�C�`���[�A���{���A�Ȃ璆��!?
http://www.nikkansports.com/ns/baseball/mlb/p-bb-tp2-050119-0011.html
�������A�����R(=߃��)�l(�L��֥`)�l( �L��`)�l( ;�L�D`)�l(߁��)�l(�L-`)�l�i�EA�E�j���� !!!
�u�l�������u���[�E�F�[�u�͂Ȃ��킯������v���āA�܂��m���ɂȂ���ł����ǁB
�I���b�N�X�͖��O���u�I���b�N�X�E�o�t�@���[�Y�v�ɂ��Ď��s�ł����ȁB�u�ߓS�E�u���[�E�F�[�u�v�ɂ��Ă���C�`���[�߂��Ă���������
�������Ă݂�ƁA�������đ厖�ł��ȁB
�w���`�@��x�i�A�[�T�[��w�C���[�A�n���J�����Ɂj
2005�N01��18���i�j
��N11���ɂ��S���Ȃ�ɂȂ����A�[�T�[�E�w�C���[�̃x�X�g�Z���[�B
��������������N�A���̓o�n�}�ɈڏZ�����Ƃ����B
�Ȃɂ��A������9�����ېł���Ă��܂��ɂȂ��Ă����Ƃ�������A�����������낤�Ȃ��B
�r�W�l�X�W�����v�Łw�O����L�x�Ȃ鏫�����̘̂A�ڂ��n�܂����B
http://bj.shueisha.co.jp/article/gedou/index.html
�ǂ�ł݂����A���̏ꍇ�A�A�}�`���A���v���ɏ��Ƃ����̂͒������������A�܂��A���������A�}�`���A�́A����ȁu�₳����v�����ł͂Ȃ��A�t�c�[�̊w������Ƃ��Љ�l�ł���A������Ƙb�Ƃ��Ď���x�ꂩ�Ȃ��Ɗ������B
���̘b�̐X���i�݂����Ȋ������ނ��덡�̃A�}�`���A�Ȃ�ł͂Ȃ����H
�����āA�Â��ČÂ����̂Ƃ����̂��E�E�E
�܂��A����͂Ƃ������A��̃T�C�g�̋l�����́A���́^ �i�Ёj���{�����A�� �Ƃ̂��Ƃ����A�P�}�ʂ��Ԉ���Ă���B
���������́A����Ȑ}�E�E�E�����������H
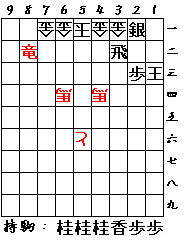
���[�ށB�T�U�ƂȂ�Ė��������悤�ȁB�����5��l����Ȃ�����
�w���₾�炯�̑�w�����x�i�O�H���v�A�W�p�АV���j
2005�N01��17���i���j
�Z���^�[�������������������āA�{�̘b��Ȃ̂œǂ�ł݂��B
�͍��m�W�҂ɂ���w�������ւ̔ᔻ���Ȃ̂����A�u�\���Z�ɂƂ��ē������͑�ȉc�Ɗ�Ղł���v�i�{��15�y�[�W�j�Ƃ������l���̕��X����̏������Ȃ̂ŁA�b�����ɕ�����������Ȃ��B
�������A�悭����Ƃ��������B
���Ƃ��A���w�̈���Ƃ��āA����Ȗ�肪�Љ��Ă���B
| (������w�@���w���i�O���j�X�W�N�x�j
�u�����Q���傫�����R���Ƃ���Ƃ��Ax^n+y^n=z^n����������x,y,z(xyz��0)�͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����̂̓t�F���}�[�̍ŏI�藝�Ƃ��ėL���ł���B�����������̐��w�҂̓w�͂ɂ�������炸��ʂɏؖ�����Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪1995�N���̒藝�̏ؖ������C���X��100�y�[�W�����_���ƁA�e�C���[�Ƃ̋����_���ɂ��^����ꂽ�B
���R�Ax^3+y^3=z^3����������x,y,z�͑��݂��Ȃ��B
���āA�����ł̓t�F���}�[�̒藝��m��Ȃ����̂Ƃ��āA�����ؖ�����B
x,y,z��0�łȂ������Ƃ��A����������x^3+y^3=z^3���������Ă���Ȃ�Ax,y,z�̂������Ȃ��Ƃ���͂R�̔{���ł���B
|
����ɂ��āA���̖{�̍�҂́A
|
��蕶�̑O���Łu�����Q���傫�����R���Ƃ���Ƃ��Ax^n+y^n=z^n����������x,y,z(xyz��0)�͑��݂��Ȃ��v�ƌ����Ă���ɂ�������炸�A�㔼�ł́u������̂Ƃ��āv�������Ă���̂����������B�u�Ȃ��v���Ƃ̏ؖ��ɂȂ�̂Ȃ�Ƃ������A�{��̐ݒ�͕s���R�ł���B
|
�ȂǂƃR�����g���Ă���B
�������A���w�ł́A�u�w���@�v�ŏؖ�����ۂɂ́A�����ƈႤ����Ɋ�Â��v�Z����̂��퓹���B������A���������_���ł���\�͂́A���w�̑f�{�ɕK�v�Ȃ��Ƃł���A�t�Ɍ����A�������������w����x�Ƃ��s���R���Ƃ�����������́A�͂����茾���Đ��w�ɂ͌����Ă��Ȃ��Ǝv���B
�������A���̒��҂́A�u�u�Ȃ��v���Ƃ̏ؖ��ɂȂ�̂Ȃ�Ƃ������v�ƁA�_�|�̓�����������Ă���B
���������A�u�Ȃ��v���Ƃ̏ؖ��́u100�y�[�W�����_���v�Ȃ��ĂB������������Ȃ��B
����ɁA���̖��ł͂��Ⴀ��ƁA�u�m��Ȃ����̂Ƃ��āv�ƒf���Ă��邩��A�ʒi�s���R�ł͂Ȃ��Ǝv���B
�ނ���A�w���ɐ��w�j��̈̋ƂƁA�_��ŖL���Ȓ��z��^����A�e�ȗǖ�ł͂Ȃ����B
������w����x�ƌ��������e������z���グ�Ď��ɗǎ��߂������̂������đ�w�ɒ@������ł���킯�ŁB
����A�}�A��͐�ő����i��j��A�S�A���ł����B
�O����R�A�����������A���͂�u������̃v����苭���v�Ƃ����̂́A�����Ȏ����Ȃ�ł��傤�ȁB
�ᓇ���E�]�@�w���{�����p�ꎖ�T�x�����c�וv�E�ďC
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/shougi/news/20050116ddm015070114000c.htm
���Ƃ��A�S���t�p�ꎖ�T��������A�u�C�[�O���v�u�h���[�v�u�e���v���v�u�e�B�[�v�u�O���[���v�uOB�v�u�A�h���X�v�Ƃ����悤�ȁA���ʂƂ͂�����ƈႤ�g�����̗p�ꂪ�����āA���{��ɖL���ȍʂ��^���Ă���B
�����A���������S���t�p��Ə����p��Ƃł́A���̕K�v���ɂ����ԈႢ������B
�f�l�S���t�@�[�ł��ł�����u�t�H�A�[�I�v�Ƌ��Ԃ��A���܂�����u�I�[�P�[�v�Ƃ������̂́A���������R�g�o���A�v���[���X���[�Y�ɂ��邩�炾���A�����ŋ������Ă��鏫���p��u�������v�u�]���Ă���v�u�ʔ����v�u�h�i����j���v�u���������v�Ȃǂ́A�������w�����Ƃɂ͒��ڕK�v�Ȍ��t�ł͂Ȃ����A���ʂ̗p��Ƃ������A�u���p��v�A���邢�́u�B��v�Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ł́B
�ǂ�ł݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ�����ǁA�w�����B�ꎖ�T�x�Ȃ̂����B
�Ƃ���ŁA�u�p���c��E���v�Ƃ͂����Ȃ�Ӗ����A�l���Ă���Ƌl�������ł����B
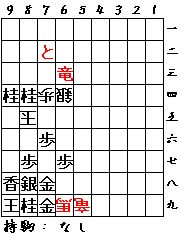
23��l�B�����Ȃ�p���c��E���ł͋l�܂Ȃ��̂Œ��ӁB
�w�Q�O�X�X �i�S�j�����x�i�W�����E�s�[���A�Ёj
2005�N01��16���i���j
�Z���^�[�����̖�肪���鋳�ȏ��Ɍf�ڂ���Ă������Ƃ܂�ܓ����ŁA�ގ��̖����ڂ��Ă����炵���B
�l�����ł����Ȃ�A�ގ���ł��ȁB
�Ђǂ��ȁ[�Ƃ͎v�����A�悭������2000�N���s�̋��ȏ�������A���܂�e���͂Ȃ���Ȃ����Ȃ��B
�l�����I�茠���A�o�葤�Ƀ~�X�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B(���͋��N�͂������j
�ƁA�����킯�ŁA�o��}�̃`�F�b�N���s���B�Ă�[���A�����Ă݂�B
�ʔ����B
��������̃C�W�����Ȗ�肾���Ă����Ă��ǂ������Ȃ��̂����i�͂����茾���āA���������͔̂z�u���Z�b�e�B���O���āA�`�ؐ搶�ɓ����������Ă��炤�A�Ƃ��łł��邵�j�A����Ȃ̂͂܂������Ȃ��B
������A�����Ղ��B�����Ċ����ł���B
�ЂƂ�ł������̐l�ɁA�������������ė~�������̂��Ǝv���B
NHK�t�͐��L���Ɍ��������A�I�Ղ̓����ň��肪�o�ċv�۔��i����C�ɋt�]�����B�L���Ƃ����Ă��A���F�̑̐��͕���Ă����킯������A���قǂł͂Ȃ������̂����B
�Ƃ���ŁA������NHK�t�̉���͍��������Ɛ�t�O�i�������̂����ǁA�����̃I�[�v�j���O�ɁA���m�����肷��V�[���������āA�Ō�ɋv��NHK�t�I�茠�҂��V����̂����A����ɂ��āA���������́A�u�D������ƁA����Ō�ɏo����ɂȂ��Ă��Ă����܂����v�Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ă����B
����ɑ��A��t�����́u�����搶���A����o�Ă��邶��Ȃ��ł����B���̑��吨�Łv�ȂǂƁB
���������B���̑��吨����Ȃ��ă^�C�g���ێ��҂�����o�Ă�̂���[�ɁB
���������匾�͎������^�C�g���Ƃ��Ă���E�E�E
�E�E�E�������l���1�ǂ́A�����O������t�����������Đ揟�B
���߂ۂ����B
���Ȃ݂ɁA�����I�[�v���ihttp://www.asahi.com/shougi/�j�ŁA��L�̋l�����I�茠�ҁE�{�c�֎j�ܒi�ƁA��L��NHK�t�I�茠�ҁE�v�ۗ������i���킢�A�u�X�[�p�[�����N�v�{�c�ܒi���������Ă���B�����������N���������B
�w�ڂ���͋���ɖ������x�i�㉓��_���A���ԃf���A�����Ɂj
2005�N01��15���i�y�j
�܂��܂��ʔ������ǁA�ǂ����w�}�g���b�N�X�x�ƃJ�u���Ă��܂��Ȃ��B
�w�}�g���b�N�X�x�ŃU�C�I�����ƃ}�V�[�����́A�Ό������m�ɐl�ނ̉^����q�������x���Ō����悤�ɂȂ������ɂ́A���̍�i�͏�����Ă����킯������A�������炵�āA���܂������ݒ�ɂȂ��Ă��܂��������Ȃ낤���ǁB
����͂���ȏ�ɂԂ��Ƃݒ�ɂȂ��Ă���B
���������Ӗ��ł́A�����������̂��B
���X�g�͂��܂��������A�}�g���b�N�X�����܂������������B
��Q��l�����I�茠���A3��6���ɊJ�Â����B
�ē��͂����灨http://www.wombat.zaq.ne.jp/propara/solving/announcement.html
���Ȃ݂ɁA�{�c�֎j�v������������P��̌��ʂ͂����灨http://www.wombat.zaq.ne.jp/propara/solving/SolvingShogi1.htm
������ō��̍�i���������Ǝv���B
�Z���^�[��������������n�܂������A�����͂܂����������E�E�E�Ƃ������A�����̖��l��̂悤�ɐ�捂ȋ�Ԃ��B
�݂Ȃ���������őS���]���l�����̉�}�ɒ�������ł݂܂��H����̓`�����s�I����Ƃ͕ʂɁA��ʐ���J�Â���܂��B�����҂��I
�܂��Ȃ���_��k�Ђ���10�N�Ƃ̂��ƂŁANHK�����Ԃ�����Ă��āA�����O���J�얼�l�ɃC���^�r���[���Ă����B
�ԑg�����������A10�N�����Ă��������Ă��Ȃ��Ƃ����������B
�s���������錾�Ȃ�ďo���Ȃ��A�ƁB
�_�˂͂������v�ł���Ƌ�����������A���݁A����ɋ���ȏɂȂ��Ă���Ƃ�����A�E�C���N���Ă���̂ł͂Ȃ����B
�_�˂ƁA�܂��C���h�l�V�A�E�X�}�g�����n�k�̊e���ցA�����̕������F��A�u�t�b�R�E�v�l���B
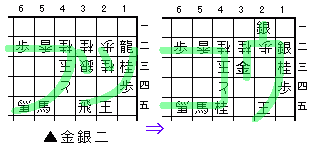
13��l�B�u�����v�Ƃ������ƂŁA�ʂ����̈ʒu�ɕ��A���ċl�ނ悤�ɂ��Ă݂��B
�w�ǓƂ̉̐��x�i�V���r���A�V�����Ɂj
2005�N01��14���i���j
���c������A�����ł����B
�E�B�L�y�f�B�A�̃v���t�B�[���A�Ȃ��Ȃ��g������B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%89%E7%94%B0%E3%81%8B%E3%81%8A%E3%82%8B
����́A12�̓����搶�̍�i���������������A���̕������̂��납��A�����������̂������̂ł��ȁB
�������ʂ̗`�Ȃ����ŁB���߂łƂ��������܂��B
�Ƃ肠�����A�j��l������Ă݂��B27��l�B
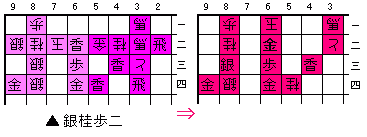
�Ƃ���ŁA��g��̓s���Ńv���u������p���_�C�X�̒S�����~��邱�ƂɂȂ����B
�c�O�����ǁA�d���̓s���Ȃ̂ŁA�܂��d�����Ȃ��Ȃ��B
�����̍X�V��~�́A���S�ɐ����a�i�ӂ��ȁj�����ǁA����A�d���̓s���ł�����ƍX�V��~�Ƃ������Ƃ����肻���B
�w���m�E���̐��E�x�i�����M�F�A�u�k�Ёj
2005�N01��13���i�j
�ЂƐ̑O�̏����w���̘b�B
�A�}�ƃv���̍����ł��������A�����ɂȂ�Ȃ��A�Ƃ������Ă���A�u���̊�������B
���҂͊��ݏZ���������߂��A���̊��m�̘b�肪�����悤�Ɋ������B
������i��12�̂Ƃ��̍�i���ڂ��Ă����B
�������Y��(59��l�j
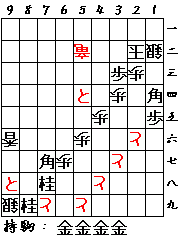
12�ł���قǂ̍�����̂ɂ���Ƃ́A���������Ǝv���B
�w�u���C���E�h���b�O�x�i�A�����E�O�����A���t���Ɂj
2005�N01��12���i���j
��������كz�[���y�[�W�ɁA�u�l-�P�O�����v���e�O�S�v�̂P���̌��ʂ��f�ڂ���Ă���B
http://www.kansai-shogi.com/event/t1-r1.htm
����͂ǂ����A�\���r���O�E�V���E�݂����ɂP�P�ł�鑁���������̂悤���B
�����A�l�������ƁA�p���ɋL���Ƃ����i���ɂȂ�̂ŁA#2�̃L�[�������\���r���O�E�V���E�ɔ�ׂ�ƁA�V���E�Ƃ��Ă̋ٔ����ɂ͌����邩�Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA�v���u�����E�p���_�C�X�̍ŐV���̋e�c���ɂ����ł��A�\���r���O�E�V���E�ɂ��āA�u�ǂ��ł��ǂ����Ƃł����A���̓X�C�b�`�������ƕЕ��̃����v���������Ŕ��ɒn���Ȃ̂ŁA�A�����J���f�E���g���N�C�Y�̑������n�b�g����������Ǝv���܂����B���N�N�������Ă��܂��H�v�ȂǂƏ�����Ă���B
�܂��A�\���r���O�E�V���E�͂���Ȋ����Ȃ̂��B
���Ȃ݂ɁA�l�����I�茠�͍��N���J�Â����B�o��́A��c�g��E�ᓇ���E���ѕq���E���Ǝ��Ƃ��������o�[�B
����ᓇ�搶�́A����͂���܂肽���������Ă��Ȃ����Ƃ�����A��c�E���ђ��S�ɂȂ邩���B
�J�Ó���3��6���i���j�Ƃ̂��ƁB�Q���҂������܂��悤�ɁB
������͉H�����⑹�̍U�߂�ʂ��Đ揟�B
���͐X�������͕s���Ȃ̂����B�Ƃ������A�����������߂ɃX�P�W���[�����^�C�g�ɂȂ��Ă��邽�߂��H
�܂��A���Ԃ���Ƃ��ƐX�������l�E����������čŋ��Ə̂��ꂽ������A�H���Ƃ͂���Ȃɍ����������킯�ł͂Ȃ������̂��낤���ǁB
�w�����x�i�^�ۗT��A�u�k�Е��Ɂj
2005�N01��11���i�j
Phenix�������B��ɂ���ĂS�����̃{�����[���B
�P�R�P���͉���ƐV��o�蒆�S�B
�P�R�Q���ƂP�R�R���͍������Ŋe�܂̂��m�点���S�B2003�N�̎ᓇ�搶50�L�O�c�A�j�[�̌��ʂ����܂���ڂ��Ă���B
�P�R�S���͕]�_���S�B
�Ƃ���ŁA�ЂƂ��炢�͉����Ă݂悤�ƁA�V��̒���M.Caillaud���i�J�C���[�h���ɂ��Ă̓J�C���[���邢�̓P�C���[���߂����������ǁA���{�l�̓J�C���[�h�ł����Ǝv���B�Ȃ��Ȃ炻�̂ق������{��ł̓J�b�R��������B����̂���l�͖�������k���̂��Ƃ��x�C�W���Ə����Ȃ����j��S#7�������Ă݂�B
M.Caillaud
Phenix issue131
S#7
���������E�E�E�ǂ����Ă���ȂɈ�{���ȂH
��������f6�Ƀi�C�g���̂ĂĂ��l��ł��܂��ł͂Ȃ����B
�Ȃɂ������Ƃ��ł�����̂��ȁH
�������A�Ƃ����킯�ł��Ȃ����AC.Feather����H#2�������B������͂킩��₷���Ĕ������������B
C.Feather
Phenix issue131
H#2 3sols.
�F�k�d�c�i�ׂ͂W���S�O�O�O���~�x�����Řa�𐬗��ł����B
������ƕs�v�c�Ȃ̂́A���z�̍������A�u����ȏ㕥���Ɖ�Ђ��ׂ�邩��v�Ƃ������ƂȂ����ȁB
�����Ή��Ƃ��ẮA200���~�Ƃ�600���~�Ƃ��B
�������A����͂ǂ��Ȃ낤�H
�Ⴆ���Z�@�ւ̉^�p�S���҂Ƃ��ŁA��Ђɐ����̎��v�v���������Ƃ��Ă��A��������Ƌ����ɂ͔��f����Ȃ��B���������{�[�i�X��������Ə�悹����邭�炢�ŁA���~�P�ʂ̃M�����͂��肦�Ȃ��B
����͂Ȃ����Ƃ����ƁA�m�[���X�N������B
�܂萬���̗��Ԃ��ŁA�^�p�Ɏ��s�����ĉ�Ђɐ����̑��Q���o���Ă��A�����ُ����邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�����B
���̃��X�N��w�����Ă���̂͌o�c�҂̂ق����B
�����J���Ɋւ��Č����A�����Ɏ��s������A���������Ƃ������Ƃ��ł���Ȃ�A�����ɑ��đ����̕�V�錠��������Ǝv�����A��Ђɋ߂�T�����[�}�������Ƃł���Ȃ�A��V�́A�����Ή����疳�ʂɏI����������ɂ�����������܂ł̑��R�X�g�������K�v������Ǝv����B
���X�N���҂��A���^�[����ׂ����Ǝv���B
�܂��ALED����������Ŏ����B�Ƃ����킯�ŁA�uLE��D�v�l���B
������ƕϓ������邯�ǁB
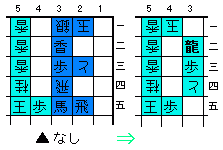
�w�Q�O�X�X �i�R�j�E���x�i�W�����E�s�[���A�Ёj
2005�N01��10���i���j
���l�̓��B
�x��܂����Ă���v���p���̌��e���쐬�B
���e�̂ق��͂����ԓ�����Ƃ���̍�i�������Ă����̂ŁA���̋@��Ɉ�ĕԑ����悤�Ǝv�����B
�s���S��͂��������ǁA�����ƒu�����ςȂ��ɐ����Ă���̂́A�C�O���e�ł�������ƈ������B
�����A�ȒP������̂��o�肷��Ɓu�S���̗p���Ȃ�������Ȃ��́H�v�Ȃ�ĕ�����邵�A���Ƃ����ē���̂��o���Ɖ҂����Ȃ�������B�܂��A�v���u�����̌���͂���Ȃ��̂ł����B
�@�c�A�����ł����B������N���炢�����Ă��Ȃ�����ɕ�����Ƃ����͖̂��������B
�����͔��Q�����A������Ɨ��ꂪ�ǂ��Ȃ��ł��ȁB
�}�b�N���2-3�����A�T�C�[�������t�@�X�g�t�[�h�X�W�J
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050105AT2F2901V05012005.html
�}�b�N�������Ƃ������Ƃ́A�����炭�}�N�h�������ƂƂ������Ƃ�ȁB���ґ�B
�w�����̗x��q�x�i���c�N�A�u�k�Ёj
2005�N01��09���i���j
�y�����ǂ߂��B
�w�t���ˁx�́A�w�]�˂ނ炳�����}�x�Ƃ����R�����ǂ߂�l�łȂ��ƁA�{���Ă��܂���������Ȃ����B
NHK�t�͒���VS�J��Ƃ���16�����lVS17�����l�̐킢�B�������ɗ͒ʂ�J����������������B
��ʃ��J�֍s���āA�T�������Ɖ��{����Y���̋l������i�W�w���n���x�i���܂���ׂ����j���w���B
�܂��A���X�_�Ђւ���������ł̏��w�B���݂�������g�ł��ǂ��B
�T�������́A���R�Ȃ���V�����̋L�����g�b�v�B
�l�������[�^���[�́A�V�N�炵���A�i�i���P�̎��A�ȋl�u��v�A�ȋl�u�P�v�ƂP�Â����Ƃ́A�������B
���X�̂�����܁i���X�a�q�j���S���Ȃ�ꂽ�������B
�f��]�_�ƂƂ����ƁA���쒷���␅�쐰�Y�݂����ȁA���Ƃ��Ɖf��Ɋւ���Ă������ƁA�������Ƃ��l���~�݂����ɁA���Ƃ̓^�����g�������������āA�ǂ��炩�Ƃ����ƌ�҂Ȃ̂��Ȃ��Ǝv���Ă�������ǁA�����ł��Ȃ��݂����B
�f��Ƃ����A�u����Ȃ�W���s�^�[�v��u�S�W���v���肪�����f��ē̋��{�K������i�l�����W�҂̂��̕��ł͂Ȃ��j���A���S���Ȃ�Ƃ̂��ƁB
�Ȃ��N�����N�̂��Ђ������Ă���̂����B
�����������F�肢�����܂��B
�w�Q�O�X�X �i�Q�j����x�i�W�����E�s�[���A�Ёj
2005�N01��08���i�y�j
�悤�₭�x�݂łЂƂ����B
��������T�{���Ă����X�V�����炩���B
�܂��A�v���p���̌��e�Ƃ��I�茠�̍�i�n��Ƃ��A�₽��ƌ���c���Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA����3�A�x�����Ȃ��ƁB
�����N���X�}�X�C�x���g�̋l�����̌��ʂ����\����Ă���Bhttp://joryukishikai.com/calendar/festival_event.html
�f���ŋ����Ă���������A�N��l��u�Ёv�̎��l�͎萔�����ł͂Ȃ�����A���ꂼ��P�V�ƂP�R�ɂȂ��Ă����B
����������Ă݂���A�Ֆʂ̋�͂P�Q���B
�����Ƃ�������邩��P�R���B
�ߑ㏫���̕ҏW���ŁA�l������Ƃ̖x���a�Y�����S���Ȃ�ɂȂ�ꂽ�Ƃ̂��ƁB
�����u�˂ނ�˂��v�Ƃ��͓ǂo��������B
����`�̎���m�A�Ƃ����C���[�W�ŁA��ʎ̂����i�𑽂��肪�����Ă����Ǝv���B
�����������F�肢�����܂��B
�w�ދ��P�N�`�x�i�đ��\�ށA�V���Ёj
2005�N01��07���i���j
��]�˕���ɌJ��L������ق�킩���㌀�B���X�������Ȃ����A��ɂ���āA�ʔ����B
�ދ��P�N�̏����w���ɉƌ������z�������m���A�E�E�E�����ށA�^���m���v�킹�镗�e�Ȃ�ł����A�C�̂������B
������̒��팠�͔s�Ґ킩��オ���Ă����H�����A���Ŋl���B
�v���[�I�t�͂���ς��ꂭ�炢�̃n���f���Ċl��������̂łȂ���A�{���ł͂Ȃ����낤�B
�܂��ǂ����̖싅���[�O�ɂ��Ă��Ă���킯�ł͂Ȃ����B
�Ō�ɁA�������`�F�X�W�B�l�����W���s�U�B�i�����܂�ǂ�łȂ����炩�j
�wCHESS�@B���@MILAN�x�iMilan R. Vuckevich�AMIM COMPANY�j
�w�Ē��̏����x�i�Ē��M�Y�AMYCOM�������Ɂj
�w�����낤�L�x�i�͓��M�A�S���{�l�����A���j
�wMy Chess Compositions�x�iMiran R.Vukcevich�ALibrary of StrateGems�j
�w���߁@�N����L�x�i�����N���A��쏑�[�j
�w�l�Ԕ�Ԃ̋}���@�R�x�i����ҁA��쏑�[�j
���X�g�B�l�����i�`�F�X�v���u�����E�l��܂ށj�������������������Ă݂�B
�ꎞ���n�}���Č����������Ƃ�����̂ŁA���\�����B
�w�I�[�V�����E�p�[�N�̒鉤�x�i�X�e�B�[�����EL�E�J�[�^�[�A�A�[�e�B�X�g�n�E�X�j
�w�y���V���L��������x�i���a���j�A�p�앶�Ɂj���^�́w�l�����x
�w�哹�����E�l�����x�i�R�����v�A�o�t���Ɂj
�w�������q�x�i���v�A�u�k�Ёj���^�́w�����E���ꂽ�x
�w匂����͍Z��Ł|���������w�������E�l�����|�x�i�ފ�����A�o�Ō|�p�Ёj
�w�l�Ԓn���x�i�֓��h�A�P�C�u���V�����Ɂj���^�́w�T���������x
�w������`��x�i�R�c�����Y�A�x�m�����Ɂj���^�́w�X�������x
�w�N�����u�R�[���x�i���{������Ƌ���A�����Ёj���^�́w��������E�l�����x(�֓��h�j
�w�����E�l�����x�i�|�{�����A�n���������Ɂj
�w�d���[�~�i�[���x�i���{������Ƌ���ҁA�����Е��Ɂj���^�́w�������l�݁x�i�������Y�j
�w���{���s�E�l�����x�i�֓��h�A�V�R���Ɂj���^�́w���������x
�w���̑o�ʐ_�x�i�����c���ҁA�����u�b�N�X�j���^�́w���N���m�x�i�X�c����j
�w���̏�̎E�l�x�i�֓��h�A�u�k�Е��Ɂj
�w�X�������J�E�l���s�x�i�֓��h�A�P�C�u���V�����Ɂj
�w�d���`�x�i�����ǁA�u�k�Е��Ɂj
�w�ʂ������x�i�c�S�Z�A���~�ЃA�E�g���[���Ɂj���^�́w����x
�w�ω��@���x�i�p�c��v�Y�A�t�z���Ɂj
�w������E�l�����x�i�֓��h�A�A�ϓ����Ɂj
�w���ܑł��x�i�]�落�v�A�o�t�Ёj
�w���ՕP�l�����n���x�i���鋱��A�V�����Ɂj���^�́w������R�[�hKUJIRA�x
�w�����喼�x�i�p�c��v�Y�A�t�z���Ɂj
�w���S�A���o�C�x(�֓��h�A�A�ϓ����Ɂj
�w�܂ڂ낵��O�x�i�p�c��v�Y�A�t�z���Ɂj
�w���S�x�i�O�D�O�A�W�p�Е��Ɂj���^�́w���ܑł��x
�����ȊO�̃��f�B�A�ł��A�l���������グ���Ă���B
5��17���̐��ˉ���w�������͓V�ˊ��m�x
�ʍ������O�}�K�W���́w�l�����p���_�C�X�x�i�ה�����j
�܂��C�tMOMO�́w��H���܂��Ă��[�I�x�i�d��Ȃ����j
�Ƃ������z�B
���N�ǂ��̈ȊO�ɂ��w������ѓ`�x�i�đ��\�ށA�V�����Ɂj�Ƃ�������B
�l�����͐��̒��ɈӊO�ƉB��Ă�����̂��B�Љ�T�C�g�ł�����Ă݂悤���Ȃ��B
�w�t���[�N�X�x�i���ҍs�l�A�����Ёj
2005�N01��06���i�j
�W�������킯������̂�������B
�w���ȕ���x�i�Ԗ{���A���w�فj
�w�y�g���X�����Ɓu�S�[���h�o�b�n�̗\�z�v�x�i�A�|�X�g���X�E�h�L�A�f�B�X�A�n���J���E�m���F���Y�j
�w�^���̑��q�x�i�W�F�t���[�E�A�[�`���[�A�V�����Ɂj
�w���a�̗w��S�W�x�i���㗴�A�W�p�Ёj
�w�u���b�N���C�g�x�i�X�e�B�[�u���E�n���^�[�A�}�K�Ѓ~�X�e���[���Ɂj
�w���ł��x�i�V�����E�T�A���쏑�[�j
�ǂ������Ƃ����ƃ~�X�e�����낤�Ƃ����̂��������Ă��邯��ǁB
�������߂͂�͂艺�Ȃ��ȁB�f��̃q�b�g�Ń��W���[�ɂȂ������������ǁB
��������Ȃ��{�ł́A
�w�A�z�Ń}�k�P�ȃA�����J���l�x�i�}�C�N���E���[�A�A�����[�j
�w�����Ɏア���Ȃ��̋����قNJ댯�Ȑ����x�i�Q���g�E�M�[�Q�����c�@�[�A���쏑�[�j
�w��Ղ���r�W�����ցx�i�H���P���E���k����A���Y�t�H�j
�w�̂������w�@�K�C�ҁx�i�{��B�Y�ATBS�u���^�j�J�j
�w������L�x�i�����O��A�_�C�������h�Ёj
�w�Ȋw���閃���x�i�Ƃ������k�A�u�k�АV���j
�Ƃ������Ƃ��납�B�w������L�x�͇�d(��ͥ)��!!
�w���X�x(�����������A�����V���Ёj
2005�N01��05���i���j
�������̔M���킢�Ƃ������A���������ǂ�ǂ�Ƃ����̂��A���܂ɓǂނƖʔ����B
�r�e�́A���͂��܂�ǂ�ł��Ȃ��B
�w���@�����e�B�[�i�x�iJ.�f�B���[�j�C, M.�X�e�B�[�O���[ �A�V�����Ɂj
�w�d���`�x�i�����ǁA�u�k�Е��Ɂj
�w�P���x���X��܂̎�x�i�W�[���E�E���t�A�������s��j
�w�s�v�c�̂ЂƐG��x�i�V�I�h�A�E�X�^�[�W�����A�͏o���[�V�Ёj
�Ƃ������Ƃ��납�B
�������A�w�d���`�x�͋l�����������Ă�����ꐫ���炠���Ă��邪�A�V���S���ǂނ̂̓^�C�w�����Ǝv���B
�z���[�͌��\�ǂ�ł���B
�w���X�g�E���@���p�C�A�x�i�z�C�b�g�j�[�E�X�g���[�o�[�A�V�����Ɂj
�w�m�ځx�i����A�W�p�Ёj
�w���C���E�K�[���Y�x�i���C�E�K�[�g���A���t���Ɂj
�w���R�E�l�x�i��Ό\�A�p��z���[���Ɂj
�w�d���̉��@�h���L�����ҁx�i�e�n�G�s�ďC�A�|���[���Ɂj
�w���҂̑̉��x�i��Ό\�A�p��z���[���Ɂj
�w�₽���S�̒J�x�i�N���C���E�o�[�J�[�A�\�j�[�}�K�W���Y�j
���㕨�́A�p�c��v�Y�Ƃ̏o�������傫���B�Ƃ肠�����ŏ��̂�������B
�w�E�@�����`�x�i�R�c�����Y�A�u�k�Е��Ɂj
�w�Ō�̐�E�q��x�i�c�S�Z�A���~�Ёj
�w���_�����J�x�i�p�c��v�Y�A�A�ϓ��j
�w�퍑���z�ȁx(�r�g�����Y�A�V�����Ɂj
�w�X�R���s�A�x�i�A���\�j�[�E�z�����B�b�c�A�W�p�Ёj
2005�N01��04���i�j
���̃V���[�Y���p�^�[��������Ȃ��悤�ȍH�v�������ĂȂ��Ȃ����������B����オ�����Ƃ���ŁA���̊����҂��y���݂��B
��������d���B
�Ƃ����킯�ŁA�C�O�~�X�e���ҁB
�w��̈ł�҂��Ȃ���x�i���j�[�E�G�A�[�X�A�u�k�Е��Ɂj
�w�I�[�V�����E�p�[�N�̒鉤�x�i�X�e�B�[�����EL�E�J�[�^�[�A�A�[�e�B�X�g�n�E�X�j
�w�����͖邳���₭�x�i���o�[�g�E�q�E�}�L�������A���Y�t�H�j
�w�鐓��̎S���x�i�}�C�P���E�X���C�h�A���t���Ɂj
�w�������̓��x�i�W���[�W�E�o�E�y���P�[�m�X�A���앶�Ɂj
�w�t���X�g���a�x�iR�ED�E�E�B���O�t�B�[���h�A�n���������Ɂj
�w���p�t�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�A���Y�t�H�j
����̍����҂ł͒������Ă������߂ł��Ȃ��Ə��������A������͒������邯�ǂ������߂ł�����̂���B
�������܂�u�ق�킩�v�ł͂Ȃ��̂������B
�w�V��d�ρx�i����A�W�p�Е��Ɂj
2005�N01��03���i���j
�A��B
�N���Ƌl�p���Ƌ��s����ɉ����A�A�����J�̃`�F�X�v���u�����G���wStrategems�x���͂��Ă���B
�w�ǂ��悩�ȂƂ͎v���Ă�������ǁA�܂��\������ł��Ȃ��͂��E�E�E�Ǝv������A��͂�ȑOPetkov���ɑ������t�F�A���[�v���u������i���Q��f�ڂ���Ă���B��[���B
��N�ǂ{�͐����Ă݂���362���B�i�}���K�E�G���͊܂܂Ȃ��j
�܂����������Ă��傤���Ȃ��{����Ȃ̂����A�܊p�Ȃ̂ŁA�R�[�w�C�Łw���̖{���������I�x�������Ă݂�B
�܂������~�X�e����(���s��)
�w�x�߂��Ίق̓�x�i�k�X���A�����Ёj
�w�z�C�ȃM�����O���n�����x�i�ɍ� �K���Y�A�˓`�Ёj
�w�o���[����^�E���̎E�l�x(�����R���A�n���������Ɂj
�w�E���̓G���L�e���x�i���ӑ�A�����Ёj
�w����͉̂ɈÍ��x�i�~����Y�A�˓`�Ёj
�w�l�Ɛ�y�̃}�W�J�����C�t�x�i�͂�݂˂�����A�p�쏑�X�j
�w���C���K�[���x�i���鉤���Y�A�V���Ёj
�w�����b�x�i���V�ەF�A�V���Ёj
�w���C�����C���E�{�E�x�i���[���q�A�W�p�Ёj
���ƁA
�w�����͈�����̐S��T��x�i���ɍI�A�u�k�Ёj
���ǂ���������ǎl������ʂ��œǂ�ł��邩�炩���B
�������Ă݂�ƁA���́u�{�i�����v�ł͂Ȃ��u�ق�킩�����v���D�݂ȂȂ��B
�������A
�w�}�[�N�X�̎R�x�i�����O�A�u�k�Е��Ɂj
�w�����̖��{�x�i������A�����Е��Ɂj
�w�A�g�|�X�x�i���c���i�A�u�k�Е��Ɂj
�w�m���̐ϖ؉S�x�i�R�c���I�A���Y�t�H�j
�w���Z���x�i��\���V�A�u�k�Е��Ɂj
�w�o���̈����x�i�L����L���A�n���������Ɂj
�Ȃ�Ă̂��ǂ�ł͂��邯��ǁA�������Ă������߂ł��Ȃ��킯�ŁB
�Ƃ肠�����A���N�̒��g���f���{�͂܂������Ȃ��A����B
�w�u���C�_���E�}�[�_�[�x�i�֓��h�A�u�k�Е��Ɂj
���̃~�X�e���ɂ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ռ��I�ȃg���b�N���g���Ă���A�֓����̐^�����Ǝv���B
�w��̎E�l�}�Ӂx(�֓��h�A�����Е��Ɂj
2005�N01��02���i���j
�T����i������Ɓj�ƌx���������D���B�������ꂾ���ŕʂɂ���Ƃ����������͂Ȃ��Z�҃~�X�e���W�B
����������ƁA�ݒ�ɋ^�₪����B
��1�b�́w�˂��ƎE�l�x�ɂ��ƁA�T����̑�O�c�����Y�͘Z�\���Ă��āA���͂̓A�}�Z�i�B
��2�b�́w�n�}�i�X�ƎE�l�x�ŁA���̂Q�l�̑ǃV�[�����o�Ă���B
�����ł́A����x���́A�u�_�ސ쌧�x����Ƃ�����r�O�ł���B�ȑO�́A��O�c�����������Ă������A�߂���͕���ł��A��O�c�̕����������炢���v�Ə�����Ă��邱�Ƃ���A�Z�i�ȏ�̊��͂̎�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�Ƃ��낪�A��4�b�́w�C�m�R�Y�`�ƎE�l�x�̖`���ł́A�u��O�c�ƌ���ł́A���͂ɑ��ꖇ�̍��͂��邪�A�����̌x���́A�u����ł��肢���܂��v�ƁA�����I���ƁA���X�ɁA���V�Z���Ɠ˂��Ă��܂����v�Ə�����Ă���B
�����炭�A����x�����ƍߑ{���ɂ��܂��Ă���ԂɁA��O�c���͑����Ɋ��͂������āA�Z�i�i�̑���ɑ��ꖇ�̍��������̂��낤�B
�w�쌀�Ђ��ߊ�x�i�~����Y�A�n���L�m�x���Y�j
2005�N01��01���i�y�j
���Ƃ��ƁA�A��ȕv�́u�쌀�ߊ�v�������Ă݂�ƁA�ǂ�ȍ�ł�����肷��̂����A���̍�i�݂����ɁA�̂�������a���_���ɓO���Ă݂�A���������ʔ������̂��ł���̂����B
���̖{�͖��y�[�W�ɉ��o��̂����A
���y�[�W�ɋl�������o�Ă���悤�Ȑ��������́A�Ȃ����̂��Ȃ��B �����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B
�{�N���ǂ�����낵�����肢�\���グ�܂��B
�ƁA�����킯�ŁA���ƂŐ����B
���w�͕����@����F���_��(�v���X�F����_�Ёj�ƁA�T�^�I�ȉF���s�����Ђ��т��ɑ̌��B
�V�ꖜ�~�D�͂��܂肨�ڂɂ�����Ȃ����A10�~�ʂŖ����̂悤�Ɍ��Ă��镽���@���A���炽�߂Ė{��������ƂȂ��Ȃ������Ȃ��̂��B
NHK�̃y�A�}�b�`�������ς�B
�D�������͈̂����{�⍪�y�A�����A�����搶�͂ǂ����ς������B
�������킹�Ō��߂���ƈႤ����w������A�l�݂�ǂ݂������⍪�������ځ[��Ɗp���̂Ă��̂ɁA�����搶�͓��a���ăV�o���̎���w������E�E�E
�吨�ɉe���͂Ȃ������Ƃ͂����A����ŋt�]������������Ă�����A�������ɂ�������B
�z�[���ւ��ǂ�